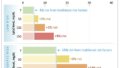はじめに:安楽死をめぐるグローバルな動向とベルギーの位置付け
安楽死や医師幇助自殺を合法化する国々では、その実施件数が着実に増加しています。オランダでは2005年の1,933件から2019年には6,361件へ、スイスでは1991年から2008年の間に高齢女性の請求が3倍、男性の請求が2倍に増加しました。こうした傾向は、安楽死に対する社会的受容の高まりや、より多くの国々が安楽死政策を導入または議論していることと関連しています。
ベルギーでは2002年5月に安楽死が合法化され、耐えがたい苦痛を伴う医学的に絶望的な状態にある成人が自発的かつ書面で要求した場合、独立した医師の承認を得て医師が積極的に患者の生命を終わらせることが可能になりました。2014年には法律が改正され、未成年者にも適用範囲が拡大されました(ただし実際の件数はごく少数です)。
この研究は、ベルギー連邦安楽死管理評価委員会(FCCEE)の2002年9月1日から2023年12月31日までの完全なデータを分析し、人口統計学的変化の影響を考慮に入れながら、安楽死件数の増加の実態を明らかにしています。
研究方法:データ収集と統計手法
本研究は、ベルギー全土で報告された33,647件(50.2%が男性、84.7%が60歳以上の世代)の安楽死事例を分析対象としています。このうち2002年の24件(法律施行直後のため)と情報不備の43件を除外し、最終的に33,580件を分析に用いました。データは医療従事者が法的に提出を義務付けられている個別報告書から収集され、完全に匿名化されています。
研究チームは2種類のモデルを比較しました。1つは人口規模を調整しないモデル(粗計数を分析)、もう1つは年齢・性別・地域別の人口規模をオフセットとして組み込んだモデル(人口あたりの発生率を分析)です。後者のアプローチにより、人口動態の変化が安楽死件数に与える影響をより正確に評価することが可能になりました。
ベルギーの言語地域別(オランダ語圏とフランス語圏)の分析に関して、患者の居住地域情報が一貫して収集されていないため、報告医師が使用した言語(オランダ語またはフランス語)を代理変数として用いるという工夫がなされています。ブリュッセル首都圏の人口については、オランダ語話者10%、フランス語話者90%と仮定して配分しています。
結果
経時的件数
分析期間中、ベルギーでは安楽死報告件数が顕著に増加しています。2003年の236件(全報告件数の0.70%)から、2012年には1,430件(4.25%)、2023年には3,423件(10.17%)に達しました。ただし2020年にはCOVID-19パンデミックの影響か、前年の2,658件から2,446件へと一時的な減少が見られました。
人口統計学的特徴
人口統計学的特徴を見ると、安楽死を選択した患者の84.74%が60歳以上で、特に70-79歳(9,251件、27.49%)と80-89歳(9,063件、26.94%)が多くを占めています。30歳未満は123件(0.37%)とごく少数です。性別分布はほぼ均等で、女性16,711件(49.67%)、男性16,902件(50.23%)でした。
年間増加率と高齢化
統計モデルの分析から、安楽死の年間増加率(RR)は1.07(95%CI、1.07-1.07)ですが、人口動態を調整した年間有病率(PR)は1.05(95%CI、1.05-1.06)となり、観察された増加の約1/4から1/3が人口構成の変化によるものであることが示されました。特に高齢化の影響が大きく、90歳以上では人口調整前のRRが0.84(95%CI、0.80-0.88)と低く見えますが、人口構成を考慮に入れるとPRは13.19(95%CI、12.55-13.86)と非常に高くなります。
時間的傾向
時間的傾向として、2003-2015年の「規制開始期」と2016-2023年の「最近期」を比較すると、RRは1.12(95%CI、1.11-1.12)から1.05(95%CI、1.04-1.06)へ、PRは1.10(95%CI、1.09-1.11)から1.03(95%CI、1.03-1.04)へと低下しており、安楽死の増加ペースが鈍化していることがわかります。これは制度が成熟し、初期の「キャッチアップ」現象が終わったことを示唆しています。
医学的理由
医学的理由としては、腫瘍(がん)が21,919件(65.14%)と最も多く、次いで多病態(5,108件、15.18%)、神経系疾患(2,650件、7.88%)が続きます。精神疾患による安楽死は427件(1.27%)、認知症は310件(0.92%)で、これらの合計は全件数の約2.2%に留まっています。
診断カテゴリーごとの変化を見ると、腫瘍に比べて多病態を理由とする安楽死が有意に増加しています(PR、1.03;95%CI、1.02-1.04)。これは、現代医学の進歩により複数の慢性疾患を抱えながら長期間生存する患者が増えていることと関連していると考えられます。一方、精神疾患や認知症に関連する安楽死件数には統計的に有意な増加は見られませんでした。
死亡場所、苦痛の種類
死亡場所としては自宅が15,770件(46.87%)で最多、次いで病院12,094件(35.94%)、介護施設4,352件(12.93%)となっています。苦痛の種類は「身体的・精神的の両方」が24,627件(73.19%)、「身体的のみ」7,989件(23.74%)、「精神的のみ」995件(2.96%)でした。
地域差
地域差については、フランドル地域(オランダ語圏)の安楽死有病率がワロン地域(フランス語圏)に比べて1.51倍(95%CI、1.47-1.55)高いことが確認されました。ただし、この格差は年々縮小傾向にあり、両地域の安楽死受容の均質化が進んでいる可能性が示唆されます。
性別
性別では、男性の安楽死有病率が女性に比べて1.36倍(95%CI、1.33-1.39)高いものの、この差も時間とともにわずかながら縮小しています(PR×年、0.99;95%CI、0.99-1.00)。この変化は、安楽死に対する社会的受容が性別を問わず広がっていることを反映しているかもしれません。
政策的含意と実践への応用
この研究から得られる重要な知見は、安楽死件数の増加を議論する際には、単純な件数の比較ではなく、人口構成の変化(特に高齢化)を考慮に入れる必要があるということです。医療政策の立案者や研究者は、以下の点を意識する必要があります。
第一に、安楽死に関する議論や報道では、しばしば「急増」「雪だるま式増加」といった表現が用いられますが、その実態の一部は単に高齢人口の増加に起因するものです。本研究の手法を参考に、人口動態を調整した分析を行うことで、より正確な実態把握が可能になります。
第二に、ベルギーのデータは、安楽死の合法化が「滑りやすい坂」現象(当初の限定された適用が次第に拡大され、倫理的に問題のある事例まで包含されるようになること)を必然的に引き起こすわけではないことを示唆しています。精神疾患や認知症を理由とする安楽死の割合が20年間にわたって安定している(全件数の約2%)ことは、適切な安全策が機能している可能性を示しています。
第三に、地域間格差の縮小は、医療サービスの均てん化や文化的受容の広がりを反映していると考えられます。この知見は、安楽死を合法化したばかりの国や地域において、実施率の地域差をどのように解釈すべきかの参考になります。
医療従事者にとっての実践的な示唆としては、高齢患者や多病態患者の増加に伴い、安楽死のリクエストに対応する機会が増える可能性があることです。特に、身体的苦痛だけでなく精神的苦痛も訴える患者(全安楽死の73.19%)に対しては、総合的な苦痛評価と多面的な緩和ケアのアプローチが求められます。
研究の限界と今後の課題
この研究にはいくつかの制約があります。
第一に、FCCEEのデータには患者の社会経済的状況に関する情報が含まれておらず、脆弱な集団への影響を評価できません。
第二に、患者の正確な居住地域情報が不足しており、より詳細な地域分析が制限されています。
第三に、報告されていない安楽死事例が存在する可能性があり、この研究の知見は公式に報告された事例に限定される点に注意が必要です。
今後の研究では、安楽死を求める患者の社会経済的背景や、医療資源へのアクセスとの関連を明らかにすることが重要です。また、COVID-19パンデミックが安楽死の実施に与えた影響(2020年の一時的な減少など)について、より詳細な分析が必要でしょう。
結論:データに基づく安楽死政策の重要性
この研究は、ベルギーにおける20年間の安楽死実施データを包括的に分析し、その増加の実態を人口動態の変化という観点から明らかにしました。重要なのは、安楽死の増加が単なる「緩やかな坂」であり、「滑りやすい坂」ではないという発見です。ベルギーでは法律制定当初から終末期に限らない疾患も対象としており、精神疾患や認知症を理由とする安楽死の割合が時間とともに増加していないことは、適切な safeguards(安全策)が機能していることを示唆しています。
医療政策の決定者や倫理委員会は、この研究の方法論を参考に、自国や自地域の安楽死データを人口動態を考慮に入れて解釈すべきです。また、安楽死をめぐる議論においては、感情的な「滑りやすい坂」論議ではなく、この研究のような実証データに基づいた建設的な対話が求められます。
医療従事者にとっては、高齢化が進む社会において、安楽死のリクエストに対処する機会が増える可能性を認識し、倫理的・法的枠組みを十分に理解しておくことが重要です。特に、身体的・精神的苦痛の両方を訴える患者が大多数を占めることから、総合的な苦痛評価と緩和ケアのスキルを磨くことが求められます。
参考文献
Wels J, Hamarat N. Incidence and Prevalence of Reported Euthanasia Cases in Belgium, 2002 to 2023. JAMA Netw Open. 2025;8(4):e256841. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.6841