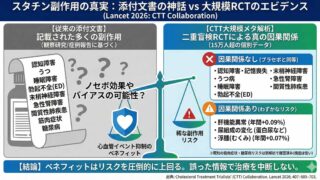 脂質代謝
脂質代謝 スタチンの添付文書に記載されている様々な副作用で、本当に起こり得るものはどれ?
はじめに 長年、スタチン製剤は心血管疾患予防の要として君臨してきましたが、同時に「副作用が多い薬」という汚名も着せられてきました。製品ラベルには、筋肉症状や糖尿病リスクのみならず、記憶障害、うつ、睡眠障害、勃起不全といった多岐にわたる項目が...
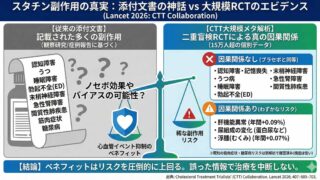 脂質代謝
脂質代謝 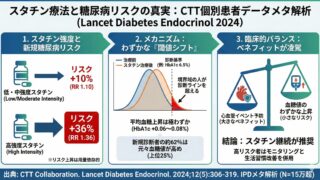 脂質代謝
脂質代謝 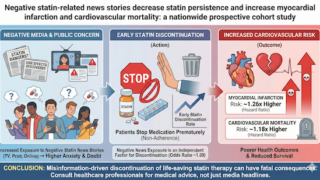 脂質代謝
脂質代謝 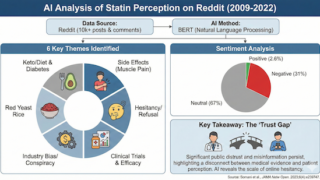 Digital Health
Digital Health  脂質代謝
脂質代謝  中枢神経・脳
中枢神経・脳  がん、悪性腫瘍
がん、悪性腫瘍  がん、悪性腫瘍
がん、悪性腫瘍  脂質代謝
脂質代謝 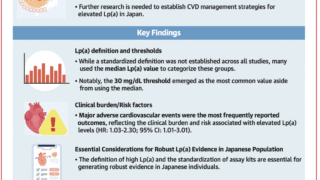 脂質代謝
脂質代謝