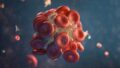はじめに
更年期に伴う血管運動症状(vasomotor symptoms: VMS)は、ほてりや発汗を特徴とし、生活の質を著しく損なう症状として知られています。ホルモン療法(hormone therapy: HT)はこれらの症状に対して最も有効な治療ですが、同時に心血管疾患(cardiovascular disease: CVD)リスクの増加が懸念され、長年議論の的となってきました。2002年のWomen’s Health Initiative(WHI)報告は、その使用を大幅に減少させた歴史的事件でした※。しかし今回の研究は、「VMSを有する女性」に限定し、かつ年齢別にHTの影響を精緻に評価した点で大きな新規性を持ちます。
※ 2002年のWHI報告は、ホルモン補充療法(HRT)が心血管疾患や乳癌リスクを増加させる可能性を示し、広く使用されていたHRT処方が世界的に急速に減少する契機となりました。
それまで「女性の健康維持に有益」と考えられていたHRTの位置づけを一変させた、いわば転換点となる出来事でした。
研究の概要
本研究は、WHIの二つのランダム化比較試験(CEE単独試験とCEE+MPA試験)の二次解析として実施されました。対象は27,347人の閉経後女性(平均年齢63.4歳)であり、子宮摘出の有無により群分けがなされています。介入は以下の二種類です。
- CEE(結合型エストロゲン)単独: 0.625 mg/日
- CEE+MPA(メドロキシプロゲステロン酢酸エステル): CEE 0.625 mg + MPA 2.5 mg/日
追跡期間の中央値は、CEE単独試験で7.2年、CEE+MPA試験で5.6年でした。主要評価項目は動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)で、心筋梗塞、狭心症による入院、冠動脈血行再建術、脳梗塞、末梢動脈疾患、頸動脈疾患、CVD死亡を含む複合エンドポイントとして設定されました。
補足:CEEとMPA
CEE(Conjugated Equine Estrogens, 結合型エストロゲン)
- 成分: 馬由来の複数のエストロゲン混合製剤。
- 役割: 更年期症状(ほてり・発汗など)を改善する主薬。
- 問題点: エストロゲン単独投与は子宮内膜を刺激し、子宮内膜癌のリスクを高める。
- 適応: 子宮を摘出している女性。
CEE+MPA(Conjugated Equine Estrogens + Medroxyprogesterone Acetate)
- MPAの役割: 合成プロゲスチン(黄体ホルモン類似薬)で、エストロゲンによる子宮内膜の増殖を抑制する。
- 効果: エストロゲンによる更年期症状改善は維持しつつ、子宮内膜癌リスクを防ぐ。
- 適応: 子宮が残っている女性。
使い分けの原則
- 子宮あり → CEE単独は禁忌。必ずプロゲスチン(MPAなど)を併用して「CEE+MPA」。
- 子宮なし(子宮摘出後) → CEE単独でよい。
つまり、CEEとCEE+MPAの違いは「プロゲスチンを併用するかどうか」であり、その選択は子宮の有無によって自動的に決まります。
血管運動症状に対する効果
CEE単独療法では、全年齢層でVMSが平均41%減少しました(RR 0.59, 95%CI 0.53–0.66)。一方、CEE+MPA療法では年齢による効果の差が顕著でした。
- 50〜59歳: RR 0.41(顕著な改善)
- 60〜69歳: RR 0.72(効果減弱)
- 70〜79歳: RR 1.20(効果消失)
つまり、エストロゲン単独は高齢者でも一貫して症状を改善するのに対し、プロゲスチン併用は高齢になると効果が失われることが示されました。この差は、加齢に伴う体脂肪率上昇とエストロゲン代謝の変化が関与している可能性が指摘されています。
心血管疾患リスクの年齢別影響
ASCVDに関しては、年齢層ごとに明確な違いが認められました。
- 50〜59歳の女性
CEE単独: HR 0.85 (95%CI 0.53–1.35)
CEE+MPA: HR 0.84 (95%CI 0.44–1.57)
いずれも有意なリスク増加は認められず、むしろ中立的でした。 - 60〜69歳の女性
CEE単独: HR 1.31 (95%CI 0.90–1.90)
CEE+MPA: HR 0.84 (95%CI 0.51–1.39)
CEE単独ではややリスク増加傾向が見られましたが、統計的に明確ではありませんでした。 - 70歳以上の女性
CEE単独: HR 1.95(217件/1万人年の超過リスク)
CEE+MPA: HR 3.22(382件/1万人年の超過リスク)
この年齢層では明らかに有害であり、特に冠動脈疾患(CHD)がリスク増加の主要因でした。
分子生物学的視点
エストロゲンは血管内皮細胞のエストロゲン受容体α/βを介し、一酸化窒素合成酵素(eNOS)を活性化して血管拡張を促進します。また、炎症性サイトカインや接着分子の発現を抑制する作用も知られています。しかし加齢に伴い、内皮機能や受容体発現が低下し、エストロゲンの保護作用が十分に発揮されなくなります。さらに、MPAはエストロゲンの有益な血管作用を相殺する可能性が報告されており、これが高齢女性でのリスク増大と関連していると考えられます。
本研究の新規性
これまでのWHI報告は「全体集団」での解析が中心であり、VMSの有無によるリスク差は十分検討されていませんでした。本研究の新規性は、「VMSを有する女性に限定し、かつ年齢ごとにHTの影響を詳細に解析した」点にあります。結果として、50〜59歳の女性ではリスク増加が認められないこと、70歳以上では明確に有害であることが示され、臨床現場での年齢別判断を裏付けるエビデンスとなりました。
臨床応用と実践的意義
- 50〜59歳の女性
VMSが強い場合、HTは安全性を担保しつつ症状改善が期待できるため、積極的に検討すべきです。 - 60〜69歳の女性
リスク増加の可能性を念頭に、心血管リスク因子を詳細に評価したうえで個別判断が求められます。 - 70歳以上の女性
ASCVDリスク増加が顕著であり、HTは避けるべきです。
患者と医師が「年齢」と「症状の重症度」を軸に意思決定を行うことが重要であり、本研究はそのための指針を明確にしました。
Limitation
- 本解析は事後的な二次解析であり、VMSの評価は自己申告に依存しています。
- 高齢女性における症例数は限定的で、推定値の信頼区間が広い部分があります。
- 多重比較による偶然の有意差が含まれる可能性があります。
- WHI試験は経口投与のCEEおよびMPAに限定されており、他の剤形(経皮、膣内投与)への外挿はできません。
結論
この研究は、ホルモン療法を巡る議論に新たな一石を投じました。50〜59歳の閉経後女性では、HTは血管運動症状を大きく改善しつつ心血管リスクを増加させないことが示されました。一方で、70歳以上の女性では明確なリスク増加が確認され、使用は強く避けるべきです。年齢層ごとに異なるリスクとベネフィットのバランスを踏まえ、臨床での意思決定に活かすことが、明日からの医療実践に直結する最も重要な知見といえます。
参考文献
Rossouw JE, Aragaki AK, Manson JE, et al. Menopausal Hormone Therapy and Cardiovascular Diseases in Women With Vasomotor Symptoms: A Secondary Analysis of the Women’s Health Initiative Randomized Clinical Trials. JAMA Intern Med. Published online September 15, 2025. doi:10.1001/jamainternmed.2025.4510