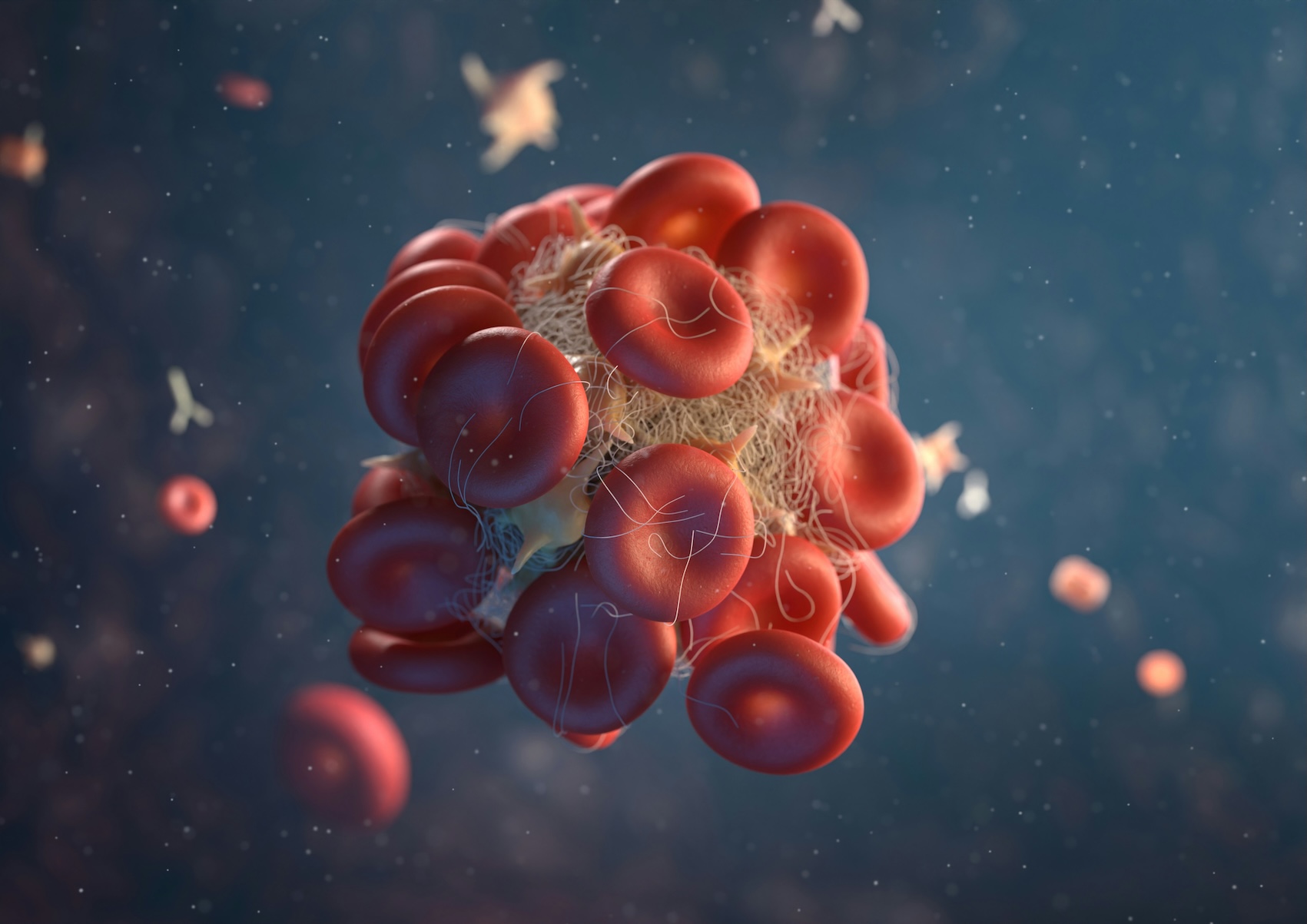序論
静脈血栓塞栓症(VTE: venous thromboembolism)は、肺塞栓症(PE)や深部静脈血栓症(DVT)を含む疾患群であり、米国では年間30万〜60万人に発症すると推定されています。VTEは適切な抗凝固療法を行えば予後改善が期待できる一方、診断が遅れると30日死亡率が最大23%に達すると報告されています。問題はその症状が非特異的である点にあります。胸痛や呼吸困難、下肢の腫脹といった症状は他疾患にも共通するため、外来診療の現場では見逃しや誤診が頻発します。
今回取り上げるKangらの研究は、この「診断遅延」という曖昧な問題を定量化するために開発された電子的臨床指標(electronic Clinical Quality Measure: eCQM)、すなわちDOVE(Delayed diagnosis of Venous thromboEmbolism)を用い、診断の遅れと死亡リスクの関連を明らかにした点で新規性があります。従来、診断遅延を体系的に数値化する仕組みは存在せず、各医療機関や研究者の経験的報告にとどまっていました。この研究は、診断の「質」を可視化し、改善可能な課題として捉える第一歩となるものです。
研究デザインと方法
研究は二つの大規模医療システムを対象としました。Mass General Brigham(MGB, ボストン, Epic EHR, データ期間2016–2021)とPenn State Health(PSH, ペンシルベニア, Oracle/Cerner EHR, データ期間2019–2022)です。両施設の電子カルテ(EHR)データを活用し、外来でVTE関連症状が記録された患者が30日以内にVTEと診断されたケースを抽出しました。
DOVE eCQMは、
- ICD-10診断コード、画像検査コード、抗凝固薬投与歴によるVTE診断の特定、
- 自然言語処理(NLP)を用いた29種類のVTE関連症状の自動抽出、
を組み合わせて診断遅延を測定します。分母は「症状あり→30日以内にVTE診断された患者」、分子は「24時間超で診断された患者」と定義され、DOVE率として算出されます。72時間超を基準にした遅延率も併せて評価されました。
主要アウトカムは診断遅延率と30日全死亡率です。死亡率は診断遅延の有無で比較され、リスク比(RR)が算出されました。
DOVE(Delayed diagnosis of Venous thromboEmbolism)の補足
DOVE eCQM(Delayed diagnosis of Venous thromboEmbolism)に関して補足します。これは 「外来でのVTE診断の遅れを電子カルテ(EHR)情報から自動的に抽出・数値化する指標」 です。
DOVE eCQMの仕組みのイメージ
1. 患者の抽出(分母設定)
- 18歳以上の患者で、外来受診時に VTE関連の症状がカルテに記載 され、
- その後30日以内に VTE(DVTまたはPE)と診断 された症例を対象とします。
- 例: 「下肢の腫脹」「呼吸困難」「胸痛」など。
→ この「症状あり+30日以内にVTE診断」が「評価対象の母集団」になります。
2. 診断までの時間を測定
- 症状が最初にカルテに書かれた「インデックス受診」から、実際にVTE診断がつくまでの時間を計測します。
- 24時間以内に診断できたか、それ以上か(あるいは72時間超か)で分類。
→ 24時間以内なら「適時診断」、それを超えると「遅延診断(Delayed)」とカウントされます。
3. カルテデータの活用
- 診断コード(ICD-10), 画像検査(CT, 超音波)のCPTコード, 抗凝固薬処方(RxNorm) で「VTE診断が確定した」ことを裏付け。
- 自然言語処理(NLP) で外来記録の自由記載から「VTEを示唆する29種類の症状」を自動抽出。
→ 構造化データ(診断コードなど)と非構造化データ(医師の記載)を組み合わせ、アルゴリズムで判定。
4. 算出方法
- 分母 = 「VTE関連症状あり → 30日以内にVTE診断」症例数
- 分子 = 「そのうち24時間を超えて診断された症例数」
- DOVE率 = 分子 / 分母
例:
100人が対象(分母)で、そのうち80人が24時間以上診断が遅れたら → DOVE率 = 80%。
5. 結果の活用
- DOVE eCQMにより、医療機関や地域単位で 「どのくらい診断遅れが多いか」 を数値化し、ベンチマーク比較が可能。
- 診断遅延の要因(医師要因・システム要因・患者要因)も併せて評価し、医療の質改善に役立てる ことが狙いです。
結果
合計3525例(MGB 3281例、PSH 244例)が対象となりました。平均年齢は約66歳、女性が約半数を占めました。
診断遅延率
診断遅延率は驚くべき高さを示しました。
- 24時間を超えて診断された割合はMGBで79.4%、PSHで82.4%。
- 72時間を超えた遅延はMGBで69.9%、PSHで71.3%。
すなわち、外来受診時に症状が記録されていたにもかかわらず、3日以上診断に至らない患者が7割に上りました。
診断遅延の要因
遅延の要因を解析したところ、最も多かったのは「医師要因」であり、MGBでは72.8%、PSHでは50%を占めました。これは、症状が既存の慢性疾患(肺疾患、心不全など)に帰属され、VTEの可能性が見過ごされていたことを意味します。システム要因としては検査予約の遅れ、患者要因としては受診勧告を守らなかったケースが挙げられました。
死亡率
死亡率に関しては、MGBで明確な差が認められました。
- 24時間以内診断群の30日死亡率は2.52%(17/675例)。
- 遅延診断群では8.33%(217/2606例)。
- リスク比は3.31(95% CI 2.03–5.38, p<0.001)。
PSHでは有意差は認められませんでしたが(RR 1.28, 95% CI 0.30–5.53)、症例数が少ないことが影響しています。
また、死亡例の多くは肺塞栓症(PE)であり、DVT単独では致死率が低いことが明らかになりました。特に「24時間以内に診断されたにもかかわらず死亡した12例」はすべてPEであり、PEが急性期死亡の主因であることが裏付けられました。
考察
この研究の新規性は、VTE診断遅延という従来「感覚的に語られてきた問題」を、EHRデータとNLPを組み合わせた電子的臨床指標で定量化した点にあります。結果は、診断遅延が極めて頻繁に生じ、しかも死亡リスク上昇と強く関連することを明確に示しました。
特に注目すべきは、診断の遅れが「検査体制の問題」ではなく「医師の認識の問題」である場合が多いことです。症状が既存疾患に紛れてしまい、PEやDVTを疑わないまま経過するケースが多発していました。この知見は、医師教育や臨床意思決定支援システム(CDS)の導入によって改善可能であることを示唆します。
さらに、DOVE eCQMの導入は、医療機関ごとの診断パフォーマンスを数値で比較可能にします。これは医療の質改善を進める上で強力な武器となり得ます。診断の遅れを「不可避な不運」ではなく「改善可能な医療の質の指標」として扱うことが、この研究の最大の貢献です。
臨床的意義と実践への応用
この研究から得られる最も重要な実践的示唆は、「外来での曖昧な症状をVTEと関連付けて早期に除外評価を行うこと」です。呼吸困難、胸痛、下肢の腫脹といった症状を安易に既存疾患の悪化と解釈せず、D-dimer測定や適切な画像検査を考慮することが死亡率低下に直結します。
また、外来においてはCTや超音波検査が即日施行できない場合も多いため、一次スクリーニングとしてD-dimer検査を積極的に活用することが推奨されます。陰性であれば低リスク群を安全に除外でき、陽性であれば迅速に専門的評価へ移行できます。
さらに、DOVE eCQMのような電子的指標を医療機関レベルで導入すれば、診断の遅れを継続的にモニタリングし、教育やプロセス改善の効果を客観的に評価することが可能です。
Limitation
本研究にはいくつかの制約があります。
- 対象は外来で症状が記録された患者に限られ、無症候性VTEは含まれないこと。
- 24時間という閾値は専門家の合意に基づくものであり、最適な時間基準が確立しているわけではないこと。
- 死亡データはEHR由来のみであり、外部死亡記録を補完していないため過小把握の可能性があること。
- VTEが後から新たに発症したのか、初診時にすでに存在していたものかを完全に区別できない症例があること。
- NLP導入は施設間で準備状況に差があり、汎用性に課題が残ること。
結論
Kangらの研究は、外来におけるVTE診断遅延がきわめて高頻度に生じ、死亡率上昇と強く関連することを明確に示しました。特に肺塞栓症は診断の遅れに直結して急性期死亡を引き起こすため、早期診断の徹底が必要です。DOVE eCQMは診断遅延を数値化できる新しい指標として、今後の医療の質改善と患者安全の推進に重要な役割を果たすと考えられます。
参考文献
Kang MJ, Schreiber R, Baris VK, et al. Delayed Venous Thromboembolism Diagnosis and Mortality Risk. JAMA Network Open. 2025;8(9):e2533928. doi:10.1001/jamanetworkopen.2025.33928