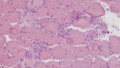序論
競技アスリートの心臓は、強度の高いトレーニングによって電気的・構造的・機能的な適応を示します。その結果、心電図(ECG)にはしばしば非アスリートには見られない特徴的な変化が出現します。洞性徐脈や房室伝導遅延、T波陰転といった所見は、病的心疾患にみられる変化と重なり合うことがあります。そのため、正常な「アスリート心」と病的心疾患をどう見分けるかは臨床上の大きな課題です。欧州心臓病学会(ESC)の予防心臓病学協会(EAPC)は、こうした診断のグレーゾーンに焦点を当て、最新のエビデンスと専門家の合意に基づいた指針を提示しました。
徐脈と房室伝導異常
アスリートでは高迷走神経緊張により洞性徐脈がよく見られます。持久系アスリートの最大80%に観察され、日中30拍/分未満の徐脈は稀ですが、睡眠中は30拍/分を下回ることがあります。引退後5年以上経過しても65%に徐脈が残存し、18%は心拍数が50/分未満のままでした。これは迷走神経優位だけでなく、洞結節自体に生じた適応的変化が長期に残存することを示しています。
房室伝導異常では、PR間隔の軽度延長は一般的ですが、400 ms以上に延長する例は稀であり、自己免疫性AVブロックや遺伝性伝導疾患を除外する必要があります。さらに日中に持続するMobitz I型二度房室ブロックも注意すべき所見で、運動や過換気で改善しない場合は構造的疾患や遺伝性心筋疾患を考慮して詳細な評価が必要です。
脚ブロックと伝導障害
左脚ブロック(LBBB)はアスリートの生理的適応ではなく、必ず精査対象です。一般集団における有病率は0.1〜0.8%と低いですが、5年間の突然死リスクは男性で10倍に上昇します。診断には心エコー(TTE)が第一選択であり、必要に応じて心臓MRI(CMR)や冠動脈CTを追加します。
右脚ブロック(RBBB)は0.2〜3%の競技者で観察され、QRS幅が130 ms未満であれば追加検査は不要ですが、130 ms以上なら少なくとも一度はTTEで構造的心疾患を除外すべきとされています。
QRS電位低下
四肢誘導でQRS電位が0.5 mV未満の場合、アスリートでは1〜2%に認められますが、心筋症や線維化の存在を示唆する可能性があります。TTE、運動負荷試験、ホルター心電図を組み合わせ、疑わしければCMRを行うことが推奨されます。
心室期外収縮
心室期外収縮(PVCs)はしばしば良性ですが、形態が多様であったり、運動で増加したりする場合には心筋症や左室瘢痕を示すことがあります。PVCが全心拍の10%を超える場合は、PVC誘発性心筋症のリスクを考慮して詳細な検査が必要です。
良性とされやすいPVCの形状
- 左脚前枝起源(fascicular PVC)
- QRS幅 <130 ms
- 不完全右脚ブロック(RBBB)型を呈することが多い
- 小児や若年アスリートにしばしば見られる
- 右室流出路(RVOT)、左室流出路/大動脈弁尖、僧帽弁輪前方部からの起源
- これらの起源は多くの場合良性で、特に単形性かつ運動で抑制されるPVCは病的意義が低いとされる
注意が必要なPVCの形状
- 広いRBBB型で上方軸を示すPVC(broad RBBB/superior axis)
- アスリートでは稀
- 左室瘢痕との関連が報告されている
- 運動で抑制されず、R on T現象を示す場合はさらにリスクが高い
- 多形性PVCや運動で増悪するPVC
- 不整脈源性右室心筋症(ARVC/ACM)や非虚血性左室瘢痕を疑わせる
- 選択的に遺伝子検査やCMRを考慮
再分極異常とT波陰転
T波陰転(TWI)は最も臨床判断に迷いを生じやすい所見のひとつです。
- 前壁誘導(V1–V3)では、16歳以上での持続は1%未満と稀です。黒人アスリートではV1–V4のTWIが13%に認められ、J点上昇を伴う場合は生理的変化の可能性が高いとされます。
- 側壁TWI(V5・V6・I・aVLにおけるT波陰転)は心筋症や線維化と強く関連しており、CMRや長期経過観察が推奨されます。
- 下壁TWI(II・III・aVFにおけるT波陰転)は意義不明ですが、まず心エコーを行い、深さ0.2 mV以上やST低下を伴う場合はCMRを考慮します。
BrugadaパターンとQT延長
Brugada症候群は突然死リスクを伴う遺伝性疾患ですが、診断的意義を持つのは1型パターンのみです。2型や3型は高位肋間での再記録で1型を除外できれば、無症候かつ家族歴がなければ追加精査は不要です。
QT延長については、男性で470 ms以上、女性で480 ms以上が診断的基準です。境界域(男性460–469 ms、女性470–479 ms)の場合は、血液検査や運動負荷試験を行い、異常がなければ年次フォローアップが推奨されます。確定的なQT延長例では、β遮断薬の導入や個別リスク評価の上でスポーツ復帰の可否を判断します。
実践的意義
この声明が示す最も重要な点は、「異常所見があっても、ただちに競技中止を指示すべきではない」ということです。臨床的に問題がないと判断されれば、年1回程度の定期的再評価を行いながら競技継続が可能です。逆に、所見が軽微でも家族歴や症状がある場合には精査を進める必要があります。医師にとっては、不必要な競技制限を避けつつ、潜在的に危険な例を見逃さないバランス感覚が求められます。
Limitation
本声明の推奨の多くは大規模前向き試験ではなく、専門家合意に基づいています。そのため科学的根拠の強さにはばらつきがあり、特に人種や性差に関する長期予後データは不足しています。また、遺伝子検査や経過観察の最適な頻度についても今後の研究が必要です。
結論
アスリートの心電図解釈は、病的異常と生理的適応の境界をどう判断するかに尽きます。今回のコンセンサスは、LBBBや高度PR延長のように「必ず精査が必要な異常」と、TWIやPVCのように「状況次第で競技継続可能な異常」を明確に区別し、臨床現場に実践的な道筋を示しました。読者にとって重要なのは、心電図の一つひとつの波形を単独で解釈するのではなく、症状・家族歴・運動反応と組み合わせて包括的に判断することです。アスリートの安全を守りながら、不要な制限を避けるための合理的かつ柔軟なアプローチが求められています。
参考文献
Finocchiaro G, Zorzi A, Abela M, Baggish A, Castelletti S, Cavarretta E, Claessen G, Corrado D, Sanz de la Garza M, Gati S, Maestrini V, Malhotra A, Niebauer J, Niederseer D, Papadakis M, Pelliccia A, Sharma S, D’Ascenzi F. Abnormal electrocardiogram findings in athletes: a consensus statement of the European Association of Preventive Cardiology of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2025;00:1–18. doi:10.1093/eurheartj/ehaf646