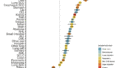はじめに
睡眠は心血管の健康を左右する重要な生活因子であり、睡眠時間や睡眠の質が動脈硬化や心筋梗塞、心不全のリスクに影響することは広く知られています。しかし「どの姿勢で眠るか」が心臓に与える影響については、ほとんど検証されていません。今回紹介する論文は、米国の大規模コホートであるSleep Heart Health Study(SHHS)のデータを用い、仰臥位睡眠時間の割合と狭心症発作頻度の関連を15年間にわたり検討した初めての研究です。この研究は、日常生活の小さな習慣である「寝る姿勢」が心筋虚血に関連しうるという新たな視点を提供しています。
研究の背景
狭心症は冠動脈疾患に由来する代表的症状であり、米国では1,080万人以上が罹患しています。胸部圧迫感や疼痛は日常生活を制限し、心筋梗塞や心不全などの重大なイベントの前兆となることもあります。狭心症のリスク因子としては、高齢、肥満、高血圧、糖尿病、喫煙歴などが知られていますが、睡眠の姿勢という行動因子については十分に研究されてきませんでした。
既存の生理学的研究では、仰臥位は交感神経活動を高め、心拍出量やストロークボリュームを増加させる可能性が指摘されています。そのため、慢性的に仰臥位で眠る習慣が狭心症リスクを高めるのではないかという仮説が立てられました。
方法
研究対象はSHHSに参加した5,804人(平均年齢63歳、女性52.3%、平均BMI 28.2 kg/m²、平均血圧127/)です。対象者は40歳以上の一般集団であり、特定の冠動脈疾患患者を限定したものではありません。降圧薬(40.1%)、経口血糖降下薬(4.1%)、脂質低下薬(12.1%)、インスリン(1.6%)を服用していました。CABG(3.7%)および冠動脈形成術(3.3%)の既往がありました。
- 睡眠評価:自宅での一晩のポリソムノグラフィー( polysomnography ;PSG)により仰臥位睡眠の割合を算出。平均して1晩6時間(359.84分)睡眠し、平均で全睡眠時間の32.4%が仰臥位でした。無呼吸低呼吸指数(AHI 13.7)は軽度でした。
- アウトカム:15年間の追跡で確認された狭心症発作回数。診断は冠動脈虚血症候群に基づき、心電図、運動負荷試験、冠動脈造影などの所見から判定されました。平均発作回数は0.48回であり、43.6%の参加者が少なくとも1回の狭心症を経験しました。
- 解析:ポアソン回帰を用いて、年齢、BMI、血圧、糖尿病、既往歴、薬剤使用などの共変量を調整。さらにBMIや性差による修飾効果も検討されました。
結果
解析の結果、仰臥位睡眠の割合が高いほど狭心症発作のリスクが増加することが示されました。
- 仰臥位睡眠時間が10%増えるごとに、狭心症発作リスクは約3%上昇(IRR=1.003, p<0.001)。
- この関連は年齢やBMI、高血圧、糖尿病などの伝統的リスク因子を調整しても独立して存在しました。
- 仰臥位睡眠と狭心症発作との関連性は、無呼吸低呼吸指数を調整した後も依然として有意でした。
- 興味深いことに、BMI(p=0.189)や性別(p=0.117)はこの関連を修飾しませんでした。つまり、肥満や男女差に関わらず「仰臥位で眠ること」自体がリスク因子である可能性が示唆されました。
- 他の有意因子としては、高齢、BMI高値、高収縮期血圧、冠動脈形成術既往、短い総睡眠時間、高い睡眠効率などが挙げられました。
考察
この研究は、日常的な睡眠姿勢が心筋虚血に関連しうることを初めて大規模かつ長期的に証明しました。平均で32%程度を仰臥位で過ごす集団において、わずか10%の増加が3%のリスク上昇を意味するのは、予防医学的に無視できない知見です。
生理学的には、仰臥位では肺や胸郭の圧迫による呼吸機能の低下、静脈還流量の変化、交感神経活動の増加が報告されています。また睡眠時無呼吸の重症度も仰臥位で増悪することが知られており、これらが冠動脈血流に悪影響を与え、狭心症のリスクを高める可能性があります。本研究でも無呼吸低呼吸指数(AHI)は境界的に有意であり、仰臥位の効果を完全には説明できませんが、一部関与していると考えられます。
さらに既存の研究では、右側臥位が副交感神経活動を優位にし、交感神経活動を抑えることが示されており、冠動脈疾患患者や心不全患者でも有利とされます。今回の結果はその知見を裏付けるものであり、睡眠姿勢が心血管リスク修飾因子となりうることを示しています。
臨床的意義と実践への応用
今回の研究は、睡眠姿勢という「修正可能な行動習慣」が心血管予防に寄与しうることを示しました。もちろん、夜間に意識的に姿勢を維持することは容易ではありません。しかし、以下の工夫が考えられます。
- 側臥位を促すような抱き枕や体位保持クッションの使用
- 睡眠時無呼吸症候群のある患者では、体位依存性の評価を行い、側臥位を推奨する
- 高リスク群(高血圧、既往冠動脈疾患)に対しては睡眠指導の一環として体位も考慮する
特に睡眠時無呼吸を併存する患者では、仰臥位回避が二重の意味で心血管保護に働く可能性があります。
この研究の新規性
これまでの研究は、睡眠時間や質と心血管疾患リスクの関連を報告してきましたが、「睡眠姿勢と狭心症リスク」を大規模前向きコホートで15年間追跡した研究は初めてです。BMIや性差とは独立して関連が確認された点も、これまでの仮説を裏付ける新しい知見です。
Limitation
- 観察研究であり、因果関係を証明するものではありません。
- 主に白人かつ高齢者集団であり、一般化には制約があります。
- 睡眠姿勢は仰臥位の割合のみ評価され、左右の側臥位や腹臥位は区別されていません。
- 睡眠姿勢の評価は一夜のみであり、習慣的な姿勢を十分に反映していない可能性があります。
- 狭心症のタイプ(安定・不安定)を区別していないため、重症度との関連は不明です。
- 不安や身体活動といった一部の交絡因子が欠如しています。
結論
仰臥位で眠る時間が長い人は、そうでない人に比べて有意に狭心症発作が多いことが示されました。これは、従来のリスク因子とは独立した関連であり、日常的な「寝る姿勢」が心血管疾患予防における新たな介入ターゲットとなる可能性を示しています。今後は機序の解明とともに、体位指導や睡眠介入が臨床実践に取り入れられるかどうかが検討されるでしょう。
参考文献
Logan JG, Byon HD, Lee Y, Kim Y, Park S, Kwon Y. Supine sleep position and angina frequency: an analysis from the sleep heart health study. Sleep and Breathing. 2025;29:326. doi:10.1007/s11325-025-03501-1.