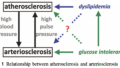はじめに
口腔機能の脆弱性(オーラルフレイル)は、加齢に伴う口腔健康状態と機能の低下を指し、全身の健康状態に深く関与しています。近年、この概念が心血管疾患(CVD)患者において特に重要であることが明らかになってきました。本解説では、Ogawaらによる2025年のスコーピングレビューを基に、口腔機能の脆弱性とCVDの関連性について、最新の知見を詳しく解説します。
この研究の新規性は、CVD患者に特化して口腔機能の脆弱性を包括的に評価した初めての大規模レビューである点です。従来の研究が主に地域在住高齢者を対象としていたのに対し、この研究ではCVD患者に焦点を当て、891,450人(うち189,461人がCVD患者)という膨大なサンプルサイズを分析しています。
口腔機能の脆弱性とは
口腔機能の脆弱性は、咀嚼や嚥下困難、口腔乾燥、歯の喪失、口腔衛生状態の悪化など多面的な症状を呈します。これらの変化は栄養不良、社会的交流の減少、生活の質(QOL)の低下を引き起こす可能性があります。特に注目すべきは、口腔機能の脆弱性が身体的な脆弱性(フレイル)の早期指標となり得る点です。栄養不良、運動不足、筋力低下といった要素と複雑に絡み合い、悪循環を形成します。
しかし、現状では口腔機能の脆弱性に対する普遍的な診断基準が存在せず、研究間で定義や評価方法に大きなばらつきがあります。このレビューでは、70の研究を分析しましたが、驚くべきことに、CVDの文脈で口腔機能の脆弱性を明確に定義した研究は一つもありませんでした。
評価方法の現状
口腔健康状態を評価するためのツールは多岐にわたりますが、標準化されていないことが大きな課題です。分析された70研究で使用された主な評価ツールは以下の通りです:
- 残存歯数:36研究(51.4%)で使用
- DMF指数(齲蝕・喪失・充填歯指数):13研究(18.6%)
- 歯周組織の評価:
- プロービング時の出血(BOP):23研究
- プロービングポケット深さ(PPD):26研究
- 臨床的付着レベル(CAL):28研究
- プラーク指数:18研究(25.7%)
包括的な評価ツールである「Revised Oral Assessment Guide」や「Oral Health Assessment Tool」が推奨されていますが、実際に使用されたのは各1研究のみでした。残存歯数は評価指標として有用ですが、口腔機能の一側面しか反映しないため、より包括的な評価ツールの開発が急務です。
心血管疾患におけるリスク因子
このレビューから、CVD患者における口腔健康状態の悪化に関連する主要なリスク因子が明らかになりました:
- 冠動脈疾患(CAD):CAD患者では口腔機能の低下リスクが増加
- 糖尿病:CVD患者で糖尿病を併発している場合、歯周炎の有病率が1.4倍高い
- 加齢と肥満:歯周状態の悪化と相関
- 感染性心内膜炎(IE):不適切な口腔衛生慣行と関連
- 炎症性マーカー:血清中の炎症マーカー上昇は歯科指数の悪化と関連
興味深いことに、この関係は双方向的です。すなわち、歯の喪失、歯周病、不適切な口腔ケア習慣は虚血性心疾患(IHD)のリスク増加と関連し、歯石やプラークはIEのリスク因子となります。また、歯周病は心不全リスクの増加とも関連しています。
予後への影響
8つの研究が、不良な口腔健康状態が心血管イベントや長期的な死亡率に与える影響を調査しました。その結果、以下のような重要な知見が得られています:
- 歯の喪失は、主要な心血管イベント(MACE)、心血管死、脳卒中のリスク増加と関連
- 不適切な口腔衛生慣行(歯科受診頻度の低さ、不十分なブラッシングやフロッシング)は、新たな心血管イベントのリスク増加と関連
- 咬筋の厚さは、術後肺炎と生存期間の優れた予測因子
特に、Reichertらの研究(2015年)では、デンタルフロスや歯間ブラシの使用が冠動脈疾患患者における新しい心血管イベントのリスク低下と関連していることが示されました。
分子生物学的メカニズム
口腔健康状態とCVDの関連には、いくつかの分子生物学的メカニズムが関与していると考えられます:
- 全身性炎症:歯周病原体が引き起こす炎症は、血管内皮機能に悪影響を及ぼし、心血管合併症のリスクを増加させます。骨吸収を促進するosteoclastの活性化を通じて、炎症が全身に波及する可能性があります。
- 細菌の血行性散布:不適切な口腔衛生慣行や歯科処置は、口腔細菌が血流に入る機会を増やし、感染性心内膜炎のリスクを高めます。
- 抗体応答:歯周病原体に対する抗体価の上昇は、全身的な炎症負荷を反映している可能性があります。
臨床的意義と実践
このレビューの知見を臨床現場や日常生活に活かすためには、以下の点が重要です:
CVD患者の包括的口腔評価
- 単なる残存歯数ではなく、歯周組織の状態、口腔衛生状態、咀嚼機能などを多面的に評価
- 可能であれば、「Revised Oral Assessment Guide」や「Oral Health Assessment Tool」などの標準化されたツールを使用
口腔ケアの強化
- 毎日のブラッシングに加え、デンタルフロスや歯間ブラシの使用を推奨
- 定期的な歯科受診(少なくとも年2回)を促す
リスク因子の管理
- 糖尿病患者に対しては特に口腔ケアの重要性を強調
- 肥満や炎症マーカー上昇患者の口腔健康状態を注意深くモニタリング
多職種連携
- 心臓リハビリテーションチームに歯科専門家を組み込む
- 入院CVD患者に対する口腔ケアプロトコルの作成
研究の限界
このレビューにはいくつかの限界があります:
- スコーピングレビューの性質上、口腔健康とCVDを結びつける特定のメカニズムを詳細に検討していません。
- 「Oral Health」というMeSH用語を使用した包括的な検索戦略であったため、一部の関連研究を見逃した可能性があります。
- 口腔機能の脆弱性の標準化された定義が欠如しているため、結果の解釈に注意が必要です。
- 地理的偏りがあり、研究の48.6%がヨーロッパ、32.9%がアジアからの報告で、他の地域のデータが限られています。
結論
口腔機能の脆弱性と心血管疾患の間には密接な関係が存在します。このレビューは、CVD患者における口腔健康管理の重要性を強く示唆しています。特に、歯の喪失や歯周病が心血管予後に関連していることから、CVD患者に対する包括的な口腔評価と適切な介入が必要です。
医療従事者は、CVD患者の治療・管理において口腔健康を重要な要素として考慮すべきです。同時に、患者自身も日常的な口腔ケアの重要性を認識し、適切な口腔衛生習慣を実践することが、心血管健康の維持・改善につながると考えられます。
参考文献
Ogawa M, Okamura M, Yagi T, Maekawa K, Amakasu K, Inoue T, Satomi-Kobayashi S, Katayama M, Muraki Y, Akashi M. Oral Health and Cardiovascular Disease ― A Scoping Review of Assessment Methods, Risk Factors, and Prognosis ―. Circ Rep 2025; 7: 223–230. doi:10.1253/circrep.CR-24-0187.