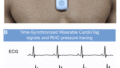はじめに
登山ブームが定着した日本では、年間およそ1,100万人がレクリエーション目的で山岳地域を訪れていると報告されています(2015年時点)。その一方で、毎年300人以上が命を落としており、その大半は警察による山岳救助の対象者です。本稿では、BMJ Open誌に掲載された大規模後ろ向き研究(Oshiro & Murakami, 2022)をもとに、2011年から2015年までに日本で救助された非生存者548名を対象とした死因別の特徴、生存可能性、そして実地医療介入の課題について解説します。
主な死因と救助時の生存率:数字が物語る過酷な現実
本研究では、548名の山岳レクリエーション中の死亡例のうち、外傷が49.1%(n=269)と最多であり、次いで低体温14.8%(n=81)、心臓死13.1%(n=72)、雪崩関連死6.6%(n=36)の順でした。
- 外傷 49.1%(n=269)
- 低体温 14.8%(n=81)
- 心臓死 13.1%(n=72)
- 雪崩関連死 6.6%(n=36)
特筆すべきは、救助隊到着時に生存が確認されたのは全体のわずか3.5%(n=19)であった点です。死因別に見ると、外傷例のうち5.2%、低体温で4.9%、心臓死ではわずか1.4%しか救助時に生きていませんでした。外傷や心停止では、1時間を超えると生存の可能性はほぼゼロとなり、低体温のみが6時間以上でも生存可能性を示しました。
年齢と性別、活動中の環境
死亡者の多くは中高年の男性でした。特に心臓死では93.1%が男性であり、全例が41歳以上でした。これは過去の欧州の山岳研究(心臓突然死の90%以上が中高年男性)とも一致する知見です。
外傷死や低体温死の多くは、岩場や積雪地帯などの危険地形で起きており、一方で心臓死の88.7%は登山道上で発見されました。これにより心臓死は比較的早期に発見・通報されやすい傾向がありますが、それでも救命には至らない例がほとんどでした。
外傷死
外傷死の94%は転落が原因であり、その内訳は頭部外傷36.4%、多発外傷35.7%、頸椎損傷7.4%などでした。特に頭部外傷では、救助時に生存していた例はわずか7.1%であり、致命率の高さが際立ちます。
外傷は「即死」に近いケースも多く、救助到着までに6時間以上要した場合、すべて死亡していました。これは「ゴールデンアワー」の概念、すなわち重症外傷においては1時間以内の治療開始が生存に直結するという基本原則を支持するものです。
心臓突然死
山岳での心臓死はほとんどが心臓突然死(SCD)であると考えられています。運動中の心拍数や血圧上昇、交感神経の過活動が不整脈を誘発し、致命的な心室細動を引き起こすことが知られています。発症から1時間以内に死亡したと推定される例が48.8%を占めており、救命の余地が極めて限られています。
通報の多くは同行者または通行人によって行われ、現場での目撃例は少なくとも25%。それでも救助時に生存していたのはわずか1例のみであり、現行の救助体制やAED設置の限界が示唆されます。
低体温:唯一、生存の可能性が残る死因
興味深いことに、低体温死では6時間以上経過していても生存例が存在しました。これは低体温が代謝を抑制し、脳や心筋の酸素消費を減らすことで延命効果を発揮するという、生理学的な特徴があるためです。実際、本研究では6名が現場での再加温処置を受け、そのうち3例は救助隊到着前にバイスタンダーによって実施されていました。
通報の約60%は、本人ではなく家族や関係者が「帰宅しない」ことで通報したものであり、これは単独行動中の判断力低下(低体温第2段階以降の意識障害)によって通報不能になることを示しています。したがって、低体温では早期通報と再加温スキルの啓発が生存率向上に直結します。
救助現場での医療介入
救助現場での医療介入は全体の31.1%にとどまり、最も多かったのはCPR(n=44)、次いでAED(n=7)、再加温(n=6)でした。しかし、CPRの質や開始時刻、蘇生成功率などは記録されておらず、実態は不透明です。
外傷例では、骨盤骨折に対する固定具の使用や、酸素投与を伴う気道確保が有効であるとされながらも、本研究では実施例が極めて少数でした。技術的制約や装備の不足、救助者の高齢化などが要因として挙げられます。
実践への示唆:明日からできる“命を救う準備”
- 登山計画は家族や知人と共有し、単独行動を避ける
- 低体温対策として、防寒具・緊急用再加温材を常備する
- 登山道での心停止に備えて、AEDの位置とCPR手順を学んでおく
- 転落リスクの高い地形では、確実な三点支持と装備を重視する
- 下山予定時刻を厳守し、日没後の行動は極力避ける
新規性とLimitation
本研究は、日本国内における山岳死亡例を死因別・時間軸別に解析し、「救助到着時の生存率」に焦点を当てた初の大規模研究である点が特筆されます。また、救助現場での医療介入の実態を具体的に示した点も、新たな知見を提供しています。
一方で、本研究にはいくつかの限界があります。まず後ろ向き研究であり、記録の欠落や地域ごとの記録方式の違いがバイアスを生む可能性があります。また、死因は医師や検死官により決定されていますが、解剖は行われておらず、心臓死などでは誤分類の可能性も否定できません。
おわりに
山岳死亡の背景には、地形・天候・年齢・既往症・通報体制・現場処置の有無といった多くの要因が複雑に絡み合っています。しかし、特に低体温においては、時間と処置によって生存が左右されうる“介入可能な死因”であることが示されました。本研究の知見は、山岳救助の現場だけでなく、登山をするすべての人々にとって重要な「命をつなぐヒント」となるはずです。
参考文献
Oshiro K, Murakami T. Causes of death and characteristics of non-survivors rescued during recreational mountain activities in Japan between 2011 and 2015: a retrospective analysis. BMJ Open. 2022;12:e053935. doi:10.1136/bmjopen-2021-053935