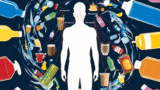はじめに
私たちの生活を支えるプラスチックは、今やあらゆる環境に浸透しています。2020年の世界のプラスチック生産量は4億3500万トンに達し、2000年の約2倍に増加しました。さらに2040年には70%の増加が見込まれており、その影響は環境だけでなく、私たち自身の体にも及んでいます。ハーバード公衆衛生大学院のMahalingiahらが2025年に発表した社説「Microplastics and Human Health」は、この“見えない汚染物質”がいかに生体に侵入し、どのような健康影響をもたらすのかを、最新の科学的知見に基づいて包括的に整理したものです。
プラスチックの化学構造と懸念される化学物質
プラスチックは、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタンなどの合成ポリマーから構成されています。これらには1万3000種を超える化学物質が関連しており、そのうち10グループが特に高い毒性を持つとされています。具体的には、難燃剤、紫外線安定剤、PFAS(ペル・ポリフルオロアルキル物質)、フタル酸エステル、ビスフェノール類、アルキルフェノール類、殺生物剤、重金属、金属類、多環芳香族炭化水素などが挙げられます。これらは可塑性を与えるために添加されますが、環境中や生体内で徐々に遊離し、内分泌かく乱や酸化ストレス、DNA損傷などを引き起こす可能性があります。
マイクロプラスチックの侵入経路
直径5 mm未満のプラスチック片は「マイクロプラスチック」と呼ばれます。環境中で分解されたプラスチックごみが空気・水・食品に混入し、人は主に吸入と経口摂取によって体内に取り込みます。
特に直径2.5 µm以下の粒子は肺胞に到達し、血流を介して全身へと分布します。
2020年にメキシコで行われた研究では、清涼飲料、ビール、紅茶、エナジードリンクなど57種類の飲料のうち48検体にマイクロプラスチックが検出されました。中でもビールでは平均28粒/Lと最も高い値を示しました。
さらに、2024年のレビューによると、化粧品・パーソナルケア製品2379点のうち16.4%にマイクロプラスチックが含まれており、特にフェイススクラブ製品では26.5%が汚染されていました。これらは使用時に微粒子を吸入あるいは誤飲する経路となります。
マイクロプラスチックの毒性機序
マイクロプラスチックが人体に与える影響は、単一の毒性経路では説明できません。むしろ、それは物理的刺激・化学的毒性・吸着汚染物質の媒介という三重のストレスによって構成されています。
1. 物理的刺激(Physical irritation)
マイクロプラスチックは直径が数µm〜数mmと、細胞や毛細血管スケールに近い大きさをもつ固体粒子です。吸入された粒子のうち、2.5 µm以下のものは肺胞深部まで到達し、マクロファージによる貪食を引き起こします。しかし、これらの粒子は分解されにくく、細胞内で慢性的な「異物反応」を誘発します。
この持続的な機械的刺激により、局所的な炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-αなど)の放出、マクロファージの活性化、線維化促進などが生じると報告されています。また、肝臓や腎臓など血流の豊富な臓器では、微粒子が毛細血管内皮を刺激し、内皮機能障害や微小血栓形成につながる可能性も示唆されています。これは、アスベストやPM2.5の慢性吸入による炎症メカニズムと部分的に類似しています。
つまり、マイクロプラスチックは「形ある異物」として物理的に細胞・組織を刺激し、免疫系の過剰反応を長期的に維持する点が重要です。
2. 化学的毒性(Chemical toxicity)
マイクロプラスチックは合成ポリマーで構成されており、その中には可塑剤・安定剤・難燃剤・フッ素化化学物質(PFAS)・フタル酸エステル・ビスフェノールAなどが含まれています。これらの添加剤はプラスチックの劣化や加熱、紫外線曝露によって徐々に遊離します。
体内に侵入した際、これら化学物質は内分泌かく乱作用(エストロゲン様活性・甲状腺ホルモン干渉)や酸化ストレスを引き起こし、細胞膜・ミトコンドリア・DNAに損傷を与えます。実際、肝臓オルガノイド研究では、ポリスチレン粒子の曝露によりALT・AST上昇、抗酸化能の低下、IL-6の上昇など、炎症性・酸化的ストレス反応が生じたことが確認されています。
このように、プラスチックは単なる物質ではなく、化学的に活性な複合体として生体に影響を及ぼします。
3. 汚染物質の運び屋(Carrier of environmental contaminants)
マイクロプラスチックは多孔質かつ親油性の表面をもち、疎水性相互作用・静電気的吸着・微細孔への取り込みによって周囲の汚染物質を取り込みます。
これには、重金属(鉛・カドミウムなど)、多環芳香族炭化水素(PAHs)、有機塩素系農薬、微生物などが含まれ、体内に入ると吸着していた有害物質を徐放する“ベクター”として働きます。
つまり、マイクロプラスチックは自身が毒性をもつだけでなく、他の環境汚染物質を体内へ運び込む「運び屋」としても機能するのです。これは、単一化学物質による毒性よりも広範かつ複合的な影響をもたらします。
総合的理解:三重ストレスとしてのマイクロプラスチック
マイクロプラスチックによる影響は、
- 固体粒子としての物理的刺激による慢性炎症、
- 化学的添加物による直接的な毒性作用、
- 他の汚染物質を吸着・運搬する媒介効果、
という3つの経路が重なり合う「複合的生体ストレス」として現れます。
この三重の負荷は、炎症反応や酸化ストレスを慢性的に維持し、血管内皮障害・動脈硬化促進・神経変性疾患リスク上昇など、多系統的な病態に波及する可能性があります。
ヒト組織での検出
驚くべきことに、マイクロプラスチックはすでに多くのヒト組織から検出されています。肺、脳、肝臓、腎臓、心臓、脾臓、結腸、精巣、卵巣濾胞液、胎盤、さらには母乳や新生児の初回便まで確認されています。
2024年の剖検研究では、ヒト脳組織中のマイクロプラスチック濃度が2016年の3345 µg/gから2024年には4917 µg/gへと増加していました。肝組織でも同様に上昇が見られています。
また、ハワイで行われた胎盤の時系列調査では、2006年の検出率60%から2013年90%、2021年には100%へと上昇。胎盤50 gあたりの粒子数は4.1個から15.5個へと増加しており(P<0.001)、人間の世代を超えて体内蓄積が進行している可能性が示されています。
疫学的関連:心血管疾患と神経変性疾患
観察研究では、マイクロプラスチックの存在と疾患との関連が明らかになりつつあります。
頸動脈狭窄症の患者257名を対象とした研究では、摘出したプラークの58.4%からポリエチレン、12.1%からポリ塩化ビニルが検出されました。検出群では34か月追跡後の主要心血管イベント(心筋梗塞・脳卒中・全死亡)の発生率が非検出群の7.5%に対し20.0%と高く、4.5倍のリスク上昇が認められました。
さらに剖検脳研究では、認知症患者12名の脳に含まれるマイクロプラスチック濃度が、非認知症52名に比べ6倍以上高値(26076 µg/g vs 4131 µg/g, P<0.001)であることが示されています。これらの結果は、血管障害や神経変性の進展にマイクロプラスチックが関与する可能性を示唆しています。
検出技術と課題
現在、顕微鏡観察、分光分析、熱分析などが主な検出手段として用いられていますが、生体サンプル中の微細粒子を確実に識別・定量するには限界があります。特に複雑な生体マトリックスからの分離や、樹脂の種類ごとの特定が難しい点が課題とされています。今後は、標準化されたプロトコルの確立と、バイオマーカー的な検出技術の開発が必要とされています。
国際社会の対応
現在、プラスチック汚染の国際的な法的規制は限定的です。2019年のバーゼル条約改正により、再利用能力の低い国への廃プラスチック輸出が規制され、またMARPOL附属書Vでは、150カ国以上が船舶からの海洋投棄を禁止しています。しかし、抜本的な対策としては2022年に始まった国連グローバル・プラスチック条約が注目されています。この条約は、プラスチックの生産から廃棄に至る全ライフサイクルを包括的に管理する法的枠組みの構築を目的としています。
臨床的・社会的インプリケーション
この論文が示すのは、マイクロプラスチックがすでにヒトの体内に蓄積しつつあり、しかもその濃度が年々上昇しているという事実です。これは環境問題にとどまらず、慢性炎症、血管内皮障害、酸化ストレスといった分子レベルの変化を通じて疾患リスクを高める可能性があることを意味します。
私たちが明日からできることは、単にプラスチックを減らすことだけではありません。ペットボトル飲料の多用を避け、化粧品や日用品の成分表示を確認する、マイクロビーズを含まない製品を選ぶなど、個人レベルでの選択も確実に曝露を減らします。加えて、医療現場や研究分野でも、生体サンプル採取時のコンタミネーション管理が今後ますます重要になります。
限界と今後の展望
現時点のエビデンスは主に観察研究と実験室データに基づいており、因果関係の確立には至っていません。また、測定技術の非標準化により研究間の比較が難しく、粒径・形状・化学組成ごとの毒性差も十分に解明されていません。
それでも、ヒトの胎盤・脳・血管における実際の検出データは、この問題がもはや仮説段階ではないことを示しています。将来的には、曝露量と疾患リスクの定量的関連を明らかにするための長期追跡研究、ならびに代替素材の開発が不可欠です。
おわりに
マイクロプラスチックは、私たちが日常的に接している「便利さ」の裏側に潜む新たな健康リスクです。分子レベルで炎症を誘発し、血管や神経に沈着するその特性は、これまでの公害とは異なり、目に見えない形で私たちの体を蝕むものです。
この論文が訴えるのは、個人・社会・国際レベルでの協働です。私たち一人ひとりが選択する行動が、将来の体内環境を決定づけるのです。
参考文献
Mahalingiah S, Nadeau KC, Christiani DC. Microplastics and Human Health. JAMA. Published online October 15, 2025. doi:10.1001/jama.2025.14718