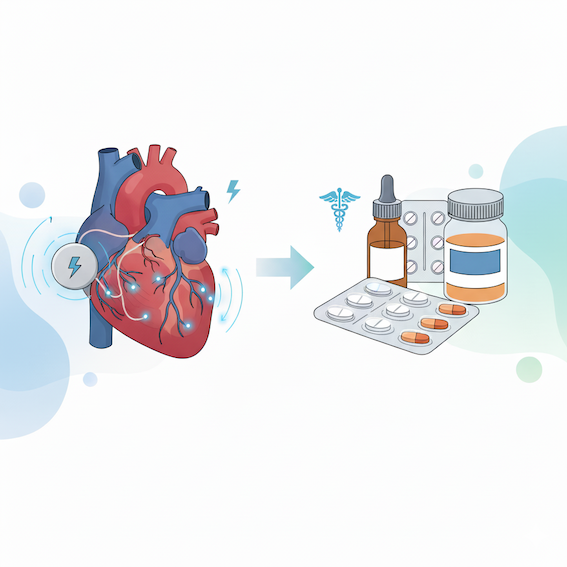序論
洞不全症候群(sick sinus syndrome, SSS)は高齢者を中心にみられる徐脈性不整脈であり、疲労、めまい、呼吸困難、失神といった症状を呈します。第一選択の治療は恒久的ペースメーカー植込みであり、生命予後や失神予防において最も確実な方法です。しかし一部の患者は、デバイスを体内に入れることへの心理的抵抗感や合併症リスクへの懸念から、植込みを拒否することがあります。そのような患者に対し、薬物療法が補助的に用いられることがありますが、十分なエビデンスはこれまで限定的でした。
本研究は、テオフィリンとシロスタゾールという二つの薬剤の陽性変時作用を直接比較した初めての臨床研究です。
研究デザインと対象
対象は2008年から2017年にかけて韓国のChonnam大学病院で診療を受けたSSS患者のうち、ペースメーカー植込みを拒否した80例です。患者はテオフィリン群(50例、200–400 mg/日)とシロスタゾール群(30例、100–200 mg/日)に分かれ、投薬4~8週間後に心拍数や症状が評価されました。平均年齢はテオフィリン群で67.4歳、シロスタゾール群で71.5歳といずれも高齢であり、併存疾患(高血圧、糖尿病、脂質異常症)の頻度には群間差がありませんでした。
SSSのタイプはRubenstein分類で、80例中70例がI型(単純な洞徐脈)、9例がII型(洞停止)、1例がIII型(tachy-brady症候群)でした。
心拍数の変化
心拍数は外来での血圧計測定値と心電図で評価されました。
- テオフィリン群では、外来測定で 53.8→65.9 bpm、心電図で 50.6→59.0 bpm と有意に上昇しました(いずれもp<0.001)。
- シロスタゾール群では、外来測定で 56.4→73.3 bpm、心電図で 54.0→66.4 bpm とさらに顕著に上昇しました(p<0.001)。
両群とも心拍数増加効果を示しましたが、統計的には薬剤間の有意差はありませんでした。注目すべきは、テオフィリンからシロスタゾールへ切り替えられた15例では、心拍数が 48.9 bpm(ベースライン)→61.4 bpm(テオフィリン)→64.0 bpm(シロスタゾール) と段階的に改善した点です。ただし切替え後の増加は有意差を示しませんでした(p=0.338)。
症状の改善
心拍数の上昇は臨床症状の改善に直結していました。全体で呼吸困難、動悸、失神が有意に改善し、特にNYHA分類でIII度以上だった37例が、治療後には7例に減少しました。
群ごとの特徴は次の通りです。
- テオフィリン群:呼吸困難と動悸が有意に改善。動悸を訴えた4例はいずれも改善しました(p=0.046)。
- シロスタゾール群:呼吸困難に加え、めまいの改善効果が顕著であり、11例中9例で消失しました(改善率82%、p=0.003)。
この「めまい改善効果」は本研究の新規性のひとつであり、シロスタゾールがテオフィリンに比べ優位性を持つ点と考えられます。
分子生物学的機序
テオフィリンは アデノシン受容体を遮断し、洞結節の自動能と房室伝導を高めます。
洞房結節には A₁型アデノシン受容体があり、アデノシンが作用すると cAMP の生成が抑制され、自動能(特に If や ICa,L 経路)が抑制されます。テオフィリンはこれを遮断し、アデノシンによる抑制を解除し、心拍数を増加させます。
一方、シロスタゾールは ホスホジエステラーゼIII(PDE-III)阻害薬です。これにより心筋内のcAMP分解が抑制され、cAMP濃度が上昇します。cAMPはPKAを活性化し、L型カルシウムチャネルのリン酸化を介して細胞内Ca²⁺流入を増加させます。さらに、sarcoplasmic reticulumからのCa²⁺放出も増強され、結果として陽性変力作用と陽性変時作用が得られます。また、If電流の活性化や血管拡張による反射性交感刺激も加わり、複合的に心拍数上昇をもたらします。
副作用と安全性
テオフィリン群では悪心5例、頭痛3例、新規不整脈3例(心房細動など)が報告されました。テオフィリンは治療域が狭く、血中濃度モニタリングが望まれる点が課題です。
一方、シロスタゾール群では頭痛4例、下痢1例と比較的軽度であり、標準用量(100 mg 1日2回)が確立しているためモニタリングは不要です。追跡期間中央値2年9か月で心血管死は両群ともゼロであり、安全性に大きな差は認められませんでした。
新規性と臨床的意義
本研究の新規性は、テオフィリンとシロスタゾールを直接比較した初めての臨床データである点にあります。従来は両薬剤の有効性が個別に報告されていましたが、比較試験は存在しませんでした。特に、シロスタゾールがめまい改善で優位性を示したことは、臨床現場にとって実践的な意義があります。
ペースメーカーを拒否する患者や、重症度が軽く直ちに植込みを要しない患者に対して、シロスタゾールは抗血小板作用と心拍数増加作用を兼ね備えた選択肢となり得ます。末梢動脈疾患を合併する高齢者においては、一石二鳥の治療薬として特に有用と考えられます。
Limitation
本研究にはいくつかの限界があります。
- 後ろ向き単施設研究であり、選択バイアス・リコールバイアスを完全には排除できません。
- 投与量が統一されておらず、効果の比較にばらつきがある可能性があります。
- 心拍数評価は外来時の心電図に限定され、24時間の変動や夜間の徐脈は評価できませんでした。
- 症状改善の評価は主観的であり、症例数の不足から統計的な有意差に限界があります。
したがって、本結果は仮説生成的な意味合いが強く、今後は前向き大規模研究が必要です。
結論と実践的示唆
この研究は、テオフィリンとシロスタゾールがSSS患者の心拍数を有意に増加させ、症状を改善することを示しました。特にシロスタゾールはめまい改善効果に優れ、副作用も比較的軽度であり、高齢者や末梢血管疾患を併発する患者において有用性が高いと考えられます。
臨床現場では、ペースメーカーを拒否する患者や導入を躊躇する症例に対し、シロスタゾールを治療オプションのひとつとして検討することが可能です。もちろんペースメーカーが第一選択である点は揺るぎませんが、患者の希望や状況に応じて柔軟に対応することが、QOL向上につながると考えられます。
参考文献
Jin I, Yoon N, Jeong HK, Lee KH, Park HW, Cho JG. Positive chronotropic effects of theophylline and cilostazol in patients with symptomatic sick sinus syndrome who have declined permanent pacing. Rev Cardiovasc Med. 2020;21(3):473–480. doi:10.31083/j.rcm.2020.03.22