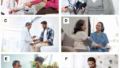はじめに
近年、たんぱく質摂取の健康影響について議論が続いています。特に動物性たんぱく質は、がんや心血管疾患(CVD)のリスクを高めるのではないかという懸念が繰り返し提示されてきました。一方で、植物性たんぱく質の摂取は健康長寿に資するとの報告もあります。しかし、これらの結論は研究デザインや解析方法により大きく異なり、統一的な見解には至っていません。本稿で取り上げる研究は、米国の代表的な疫学調査であるNHANES III(1988–1994年実施)を用いて、動物性・植物性たんぱく質の「通常摂取量」と全死亡、CVD死亡、がん死亡のリスクとの関連を詳細に検討したものです。
本研究は、先行研究の中でも大きな注目を集めたLevineら(2014)の報告と正面から対比される意義を持ちます。同研究は「50〜65歳で高たんぱく食を摂るとがん死亡が4倍に増加する」と報告しましたが、その解析方法には限界が指摘されていました。今回の研究は、より精緻な推定手法を用いて、同じNHANES IIIデータを再解析し、従来の知見を再検証した点で新規性が際立っています。
研究方法
対象は19歳以上の成人15,937人(男性7,483人、女性8,454人)で、死亡データは2006年まで追跡されました(総死亡3,843件)。摂取量は24時間リコール調査に基づき、マルチバリアントMCMC法で「通常摂取量」を推定しました。この手法は日ごとの誤差を補正し、より安定した栄養摂取量の推定を可能にします。
検討したアウトカムは以下の3つです。
- 総死亡
- CVD死亡(心筋梗塞・脳卒中など)
- がん死亡
さらに、血中インスリン様成長因子-1(IGF-1)濃度(N=5,753)も解析に含められました。IGF-1は細胞増殖や腫瘍形成に関わる分子であり、たんぱく質摂取とがんリスクを結びつける候補機序とされています。
結果
解析の結果、以下の主要な知見が得られました。
- 総死亡との関連
- 動物性たんぱく質:HR 0.99(95%CI 0.98–1.01, P=0.29)
- 植物性たんぱく質:HR 1.02(95%CI 0.95–1.10, P=0.55)
→いずれも有意な関連を認めませんでした。
- CVD死亡との関連
- 動物性たんぱく質:HR 1.02(95%CI 0.99–1.04, P=0.14)
- 植物性たんぱく質:HR 1.01(95%CI 0.91–1.13, P=0.81)
→どちらも統計的に有意ではありませんでした。
- がん死亡との関連
- 動物性たんぱく質:HR 0.95(95%CI 0.91–1.00, P=0.04)
→わずかに保護的な効果が観察されました。 - 植物性たんぱく質:HR 1.08(95%CI 0.93–1.24, P=0.30)
→有意な関連なし。
- 動物性たんぱく質:HR 0.95(95%CI 0.91–1.00, P=0.04)
- IGF-1との関連
- 総死亡:HR 1.00(P=0.81)
- CVD死亡:HR 0.99(P=0.53)
- がん死亡:HR 1.00(P=0.76)
→血中IGF-1濃度と死亡リスクには一切関連が認められませんでした。
- 年齢層別解析
- 50〜65歳群においても、総死亡やCVD死亡との関連は見られず、むしろ動物性たんぱく質はがん死亡と逆相関(HR 0.87, P=0.034)を示しました。
- 高齢群(>65歳)でも同様に関連なし。
分子生物学的視点
IGF-1は細胞の成長・分化を促進し、がん発生に寄与する可能性が指摘されてきました。先行研究では「高たんぱく食→高IGF-1→がんリスク増大」という仮説が提示されましたが、本研究ではIGF-1濃度と死亡リスクの間に有意な関連は全く認められませんでした。これは、IGF-1の作用が単純に「高いほど悪い」あるいは「低いほど良い」といった直線的関係ではなく、U字型あるいは疾患特異的な非線形性を持つことを示唆しています。
また、食事由来のたんぱく質そのものが死亡リスクを直接規定するのではなく、食事全体の質や生活習慣、炎症や代謝異常といった背景因子が複合的に影響している可能性が強調されます。
新規性
- Levineら(2014)の「中年期高たんぱく食でがん死亡4倍」という衝撃的な報告を、同じNHANES IIIデータを用いながら否定的に再検証しました。
- 通常摂取量を推定するMCMC法を用いたことで、日内変動や過小申告による誤差を補正し、より精緻なリスク推定が可能になりました。
- 動物性たんぱく質に関しては「有害」ではなく「軽度に保護的」である可能性を提示し、従来のパラダイムに修正を迫る結果となりました。
実践的意義
本研究から、一般成人において「動物性たんぱく質を摂ることが死亡リスクを高める」という根拠は支持されませんでした。むしろ、適度なたんぱく質摂取(特に動物性)ががん死亡に対して軽度に有益である可能性すら示唆されます。
臨床の現場や日常生活においては、「たんぱく質の種類を極端に制限する必要はない」ことが実践的なメッセージとなります。むしろ、全体の栄養バランスや喫煙・運動習慣といった生活因子に着目する方が合理的といえるでしょう。
Limitation
- 食事データは自己申告(24時間リコール)に基づくため、過小申告や記憶誤差が不可避です。
- IGF-1解析はサブサンプルに限られており、イベント数が少ない点は限界です。
- 追跡は2006年までであり、より長期の追跡(例えば2012年まで)では結果が変わる可能性があります。
- 栄養素の置換解析(動物性を植物性に置き換えた場合の影響)は実施されていません。
結論
NHANES IIIに基づく本研究は、動物性・植物性たんぱく質摂取が総死亡、CVD死亡、がん死亡と有意に関連しないことを明らかにしました。さらに、動物性たんぱく質はがん死亡に対して軽度の保護的効果を持つ可能性が示されました。IGF-1濃度との関連も認められず、「高たんぱく=有害」という単純化された議論に修正を迫る重要な結果です。
参考文献
Papanikolaou Y, Phillips SM, Fulgoni VL 3rd. Animal and plant protein usual intakes are not adversely associated with all-cause, cardiovascular disease–, or cancer-related mortality risk: an NHANES III analysis. Appl Physiol Nutr Metab. 2025;50(1):1–8. doi:10.1139/apnm-2023-0594.
追記(1):同じNHANES IIIのデータを使いながら、Levineら(2014)と今回の研究(Papanikolaouら, 2025)が正反対の結論に至った理由は??
Levineら(2014)の解析方法と問題点
Levineらの有名な論文(Cell Metab. 2014)は、「50〜65歳の中年期に高たんぱく食を摂ると、がん死亡が4倍以上に増える」という衝撃的な結論を出しました。しかし、この解析にはいくつかの限界があります。
- 「実測摂取量」をそのまま使用
- NHANESの食事データは24時間リコール(前日に食べたものを自己申告)に基づきます。
- 1日の記録だけでは日間変動が大きく、「その人の普段の食習慣」を正しく反映していません。
- したがって、誤差や過小申告が結果に強く影響する可能性がありました。
- たんぱく質摂取量の「恣意的な分類」
- 高(≥20%エネルギー, 約94 g/日)、中(10–19%, 約70 g/日)、低(<10%, 約42 g/日)の3群に分けました。
- この区分は「等しい人数の三分位」ではなく、著者が設定したカットオフでした。
- その結果、各群の人数が不均衡(低群437人 vs 高群1146人)で、イベント数が少ない群ではリスクが過大推定される危険がありました。
- 年齢層を限定した解析
- 特に「50〜65歳」のみに注目し、その年齢層での死亡数が限られていたため、相対リスクが大きく変動しました。
- 小さいサンプルでの解析は、信頼区間が広く、本来より誇張されたリスクを示す可能性があります。
今回の解析(Papanikolaouら, 2025)の工夫と違い
- 「通常摂取量(usual intake)」を推定
- マルチバリアントMCMC法を用いて、複数日の食事記録や共変量を統合し、「普段の平均的な摂取量」を推定しました。
- これにより日ごとの誤差が補正され、より信頼できる摂取量評価が可能になりました。
- 摂取量の扱いを連続変数に
- Levineらのように「高・中・低」に分けるのではなく、摂取量を連続的にモデル化(1g、5g、10g増加ごとのリスクを評価)。
- これにより、人数が不均衡な群分けに伴う「小さい群の過大推定」を回避しました。
- 全体データを網羅的に解析
- 全体集団(N=15,937)だけでなく、<65歳、50–65歳、>65歳といった年齢層別に解析。
- いずれの層でも「動物性・植物性たんぱく質は総死亡・CVD死亡に関連しない」という安定した結果が得られました。
- イベント数を十分に確保
- 総死亡3,843件という大規模なデータを使い、各解析で一定の統計的パワーを確保しました。
- そのため、リスク推定が過度に揺れ動くことを避けられました。
なぜ結果が真逆になったのか?
- Levineら(2014)は、
- 「実測の1日摂取」+「不均衡な3群分け」+「小さなサブ集団」
に基づき、リスクが「水増し」された可能性があります。
- 「実測の1日摂取」+「不均衡な3群分け」+「小さなサブ集団」
- Papanikolaouら(2025)は、
- 「通常摂取量の推定」+「連続変数モデル」+「全体集団での安定した解析」
により、より信頼性の高い推定を行いました。
- 「通常摂取量の推定」+「連続変数モデル」+「全体集団での安定した解析」
結果として、Levineらが提示した「高たんぱく=がん死亡リスク大幅増」という結論は再現されず、むしろ「動物性たんぱく質はがん死亡に対して軽度に保護的である可能性」が示されたのです。
まとめ
同じデータでも解析方法が違えば、結論は大きく変わり得ます。特に栄養疫学の分野では、
- データの「質」(1日の記録か、平均化された推定値か)、
- 分析の「方法」(恣意的な区分か、連続変数か)、
- 対象の「規模」(小規模サブ集団か、大規模全体か)
によって、リスク推定が大きく揺れ動きます。今回の研究は、過去の「動物性たんぱく質有害説」に対して、より慎重で安定したエビデンスを提示した点で意義深いといえます。
追記(2):「動物性たんぱく質摂取が健康リスクを高める」とする研究は数多く存在する一方で、今回の研究では真逆の結果。整合性は?
確かに、Levineら(2014)以外にも「動物性たんぱく質摂取が健康リスクを高める」とする研究は数多く存在します。例えば、赤肉や加工肉の摂取と心血管疾患やがんリスク上昇を示した前向きコホート研究は有名ですし、国際的なメタ解析でも同様の結果が報告されています。一方で、今回のNHANES III再解析では「動物性たんぱく質と死亡リスクは関連せず、むしろがん死亡に対しては軽度に保護的」という真逆の結果が示されました。では、どう整合的に理解すべきでしょうか。
1. 「動物性たんぱく質」=均一ではない
多くの研究で「動物性たんぱく質」と一括されていますが、その中身は大きく異なります。
- 赤肉(牛・豚)や加工肉(ソーセージ・ベーコン)は飽和脂肪酸や発がん性物質(ニトロソ化合物、ヘム鉄)が多い。
- 鶏肉や魚、乳製品はむしろ有益な成分(不飽和脂肪酸、カルシウム、ビタミンDなど)を含む。
多くの「ネガティブなアウトカム」を示す研究は、動物性たんぱく質の中でも「赤肉・加工肉」に強く引っ張られていることが少なくありません。今回の研究は「動物性たんぱく質全体」を栄養素レベルで解析しており、食品ごとの差異を捉えられていません。このため、「肉の種類によって結果が異なる」ことが整合性のひとつの鍵です。
2. 栄養素 vs 食品・食事パターンの違い
- 栄養素レベル(今回の研究):たんぱく質を「動物性 vs 植物性」としてエネルギー比率や摂取量で評価。
- 食品・食事パターンレベル(他研究):特定食品(赤肉、乳製品)や食事全体(Western diet vs Mediterranean diet)として評価。
つまり、動物性たんぱく質そのものは中立的でも、「それを含む食品や食事パターン」がリスクに影響している可能性が高いのです。例えば赤肉由来のリスクは、肉そのものではなく「調理法(高温調理による発がん物質生成)」「付随する脂質組成」に依存しているかもしれません。
3. 集団・背景因子の違い
研究ごとに対象集団の特徴が異なります。
- 欧米の大規模コホート:赤肉・加工肉を多食し、野菜・魚摂取が少ない人が多い。
- NHANES III:米国代表ですが、たんぱく質摂取は総じて中等度であり、極端な高摂取者は少ない。
そのため、「過剰摂取の害」を強調した研究と、「通常レベルの摂取」を扱った研究では結果が食い違うのは自然です。今回のNHANES解析は「一般的な摂取量の範囲」での評価であり、極端な高摂取群を対象とした研究ほどネガティブな関連は出にくかったと考えられます。
4. 交絡因子の扱い
動物性たんぱく質摂取が多い人は、同時に以下の特徴を持つことが多いと報告されています。
- 喫煙率が高い
- BMIが高い
- 野菜・果物摂取が少ない
- 加工食品摂取が多い
先行研究では、これらの交絡因子を完全に調整できていないケースがあり、「肉=悪い」という因果推論が過大に出ている可能性があります。今回の解析は共変量を多く調整しており、交絡の影響を可能な限り排除した点が特徴です。
5. IGF-1仮説の再検証
Levineらは「高たんぱく→IGF-1増加→がん死亡リスク上昇」というメカニズムを提案しました。しかし今回の解析では、IGF-1濃度と死亡リスクの関連は全く認められませんでした。つまり、少なくとも「通常レベルのたんぱく質摂取」によるIGF-1上昇は、がん死亡リスクを説明する決定的要因ではない可能性があります。
整合的な理解のために
- 「動物性たんぱく質そのもの」ではなく「肉の種類・調理法・食事全体」が健康リスクを規定している。
- 「極端に高い摂取レベル」ではネガティブな影響が出るが、「通常レベル」では中立~軽度に保護的。
- IGF-1仮説は単純すぎ、より複雑な代謝・炎症経路を考慮すべき。
まとめ
動物性たんぱく質に関する研究結果の不一致は、「評価の単位」「対象集団」「交絡因子調整の有無」に起因する部分が大きいです。したがって、今回の研究は「通常の摂取範囲ではリスク増加は確認されない」という重要なバランスを提示していると理解できます。一方で、赤肉・加工肉の過剰摂取や偏った食事パターンが有害であることは依然として多くのエビデンスに支えられており、両者を統合的に解釈することが求められます。