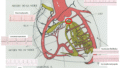序論:最大心拍数という「生理学的上限」
最大心拍数(Maximal Heart Rate, MHR)は、心拍がどこまで上がるかという「心臓の生理的限界」を示す指標であり、運動強度の設定・心肺フィットネス評価・リスク管理の基盤をなすパラメータです。
しかし、臨床現場やトレーニング現場では、すべての人に最大負荷試験(GXT;Graded Exercise Test)を行うのは現実的ではなく、年齢をもとにMHRを推定する式が長年用いられてきました。最も有名な式が 「220−年齢(Fox式)」 ですが、この式は回帰分析ではなく、複数研究の観察値を単純に線形化した経験則であり、個人差が大きいという問題が指摘されてきました。
その後、Tanaka式(208−0.7×年齢) や Gellish式(207−0.7×年齢) などが開発されましたが、依然として予測誤差は±10 bpmを超えることが多く、特に心肺体力(CRF;cardiorespiratory fitness)の高低が誤差に影響する可能性が議論されていました。
方法:7つの年齢ベース式の精度比較
対象は、2019〜2024年にジョージ・メイソン大学で最大負荷心肺運動試験を受けた健康成人230名(男性76%、平均年齢38.5±12.3歳)。すべての被験者は、
- RER(respiratory exchange ratio 呼吸交換比) ≥ 1.10
- 年齢推定MHRの90%以上
- 主観的運動強度(RPE; rating of perceived exertion)≥ 19
のうち2項目以上を満たし、「最大努力に達した」と認定されています。
評価した7つの式は以下の通りです。
- Fox(220−年齢)
- Tanaka(208−0.7×年齢)
- Gellish(207−0.7×年齢)
- Arena(206−0.88×年齢)
- Åstrand(216.6−0.84×年齢)
- Nes(211−0.64×年齢)
- Fairbairn (208 − 0.8 × 年齢(男) 201 − 0.63 × 年齢 (女))
各式による予測値と実測MHRとの差を「誤差」として算出し、線形混合効果モデル(LMM)を用いて、「式 × VO₂max × 性別」の交互作用を解析しました。さらに、Bland–Altman解析で一致度を、MAE(平均絶対誤差)・RMSE(平方平均誤差)・ICC(級内相関係数)で精度を評価しています。
結果:CRFの影響は小さく、年齢が支配的要因
LMM解析では、予測式の主効果(p<0.001)および「式×VO₂max」交互作用(p=0.015)が有意でしたが、VO₂max単独(p=0.18)や性別(p=0.49)は非有意でした。つまり、心肺体力そのものよりも「どの式を使うか」が誤差に影響しました。
モデルの決定係数は 条件付きR²=0.70、限界R²=0.02 と報告され、CRFの寄与はわずか2%程度でした。
男性では一部の式でVO₂max高値ほど誤差が増加(R²≤0.06)しましたが、女性ではその傾向は認められませんでした。誤差の平均は−3〜+6 bpmと小さい一方、一致限界(LOA)は±18〜24 bpmと広く、個人レベルでの誤差が大きいことが示唆されました。
精度指標では、Arena・Tanaka・Gellish式が最も小さな誤差を示し、Fox式は比例バイアスが最も少なく全域で安定していました。
結果の補足
少しわかりづらいので補足いたします。
1. どんな解析だったか
研究者たちは、「最大心拍数(MHR)」の予測式がどのくらい正確かを調べるために、統計モデル(線形混合効果モデル:LMM)を使いました。
LMMは、いろいろな要因が誤差にどのくらい影響するかを見分ける方法です。
ここでは主に、
- 「どの予測式を使うか(Fox式、Tanaka式など)」
- 「心肺体力(VO₂max)」
- 「性別」
の3つが、MHRの予測誤差に関係しているかを調べています。
2. 結果の意味(p値の部分)
- 予測式の違い(主効果):p<0.001 → とても有意差あり。
→ 「どの式を使うか」で誤差の大きさが変わる。 - 式×VO₂max(交互作用):p=0.015 → やや有意。
→ 「心肺体力が高い人では、式によって誤差の出方が少し違う」ことを示す。 - VO₂max単独:p=0.18 → 有意ではない。
→ 「心肺体力そのもの」が誤差の大きさに影響しているとは言えない。 - 性別:p=0.49 → 有意ではない。
→ 男性か女性かによる差はほとんどない。
つまりまとめると、誤差を左右していたのは「人の体力」ではなく「どの式を選ぶか」だった、ということです。
3. R²(決定係数)の意味
R²というのは、「このモデルで誤差をどのくらい説明できたか」という指標です。
- 条件付きR² = 0.70
→ モデル全体(すべての要因)で、誤差の70%を説明できた。
つまり、いろいろな要素を合わせれば、ある程度うまく誤差を予測できる。 - 限界R² = 0.02
→ 固定要因(=CRFや性別など)だけでは2%しか説明できなかった。
→ つまり、「体力や性別の影響はほんのわずか」という意味。
4. ここまでをまとめると
この解析からわかったのは:
- 最大心拍数の予測誤差は、その人の心肺体力や性別よりも、使う計算式の違いによって大きく変わる。
- 心肺体力(VO₂max)は影響が小さく、誤差の2%程度しか説明できなかった。
- だから「どの式を選ぶか」が最も重要であり、「体力の高い人用の特別な補正」はあまり意味がない。
5. 男性では体力が高いほど、少しズレが大きくなった
研究では、VO₂max(最大酸素摂取量)=体力の高さを示す指標として使っています。
この値が高いほど「持久力が高い」「心肺が強い」ことを意味します。
結果として――
男性では、体力が高い人ほど一部の式で誤差が少し大きくなったのです。
つまり、たとえば「220−年齢」などの年齢ベース式で出た“予測MHR”よりも、実際のMHRが高く出る人がいた、ということです。
ただし、その関係の強さを示す R²(決定係数) は 0.06以下、
つまり 6%未満しか説明できない程度で、ごく弱い相関でした。
要するに、「あくまでわずかな傾向」であって、強い関係ではないということです。
一方、女性ではこの傾向はまったく見られませんでした。
女性の場合、体力の高さに関係なく、式による誤差の大きさはほぼ一定でした。
7. 平均の誤差は小さいけれど、個人差がとても大きい
平均すると、予測MHRと実測MHRの差は −3〜+6拍/分。
つまり「だいたい当たっている」ように見えます。
でも実際には、人によってズレがかなり大きいことが分かりました。
そのズレの範囲を示すのが 一致限界(LOA:Limits of Agreement) という指標です。
この研究では、±18〜24 bpmでした。
つまり、ある人は予測値より20拍くらい高く出るし、
別の人は20拍くらい低く出る、ということです。
要するに、平均では正確に見えても、個々人の予測には大きな誤差があるということです。
このため、「最大心拍数の70%で運動しましょう」といった指導を予測値で行うと、
人によっては「まだ全然余裕」だったり「オーバーワーク」だったりするリスクがあるのです。
8. どの式が一番安定していたか
7種類の式の中で、最も誤差が小さかったのは次の3つでした:
- Arena(206−0.88×年齢)
- Tanaka(208−0.7×年齢)
- Gellish(207−0.7×年齢)
これらは、平均誤差・ばらつきともに小さく、比較的「実際のMHRに近い」値を出せていました。
つまり、現場で使うならこの3式がもっとも信頼性が高いということです。
一方で、最も古い Fox式(220−年齢) は、平均誤差はやや大きめでしたが、
「比例バイアスが少ない」=「どんな年齢層でもズレの方向が偏らない」 という特徴がありました。
つまり、若い人でも年配の人でも、Fox式のズレは比較的“均等”に起きていたのです。
このため、全体としては安定した式と評価されています。
9. ここまでをまとめると
- 男性では体力が高い人ほど、いくつかの式で「実際の最大心拍が高めに出る」傾向があった。
でもその影響は小さく、全体の6%以下しか説明できなかった。 - 女性ではその傾向が見られず、体力の影響はほとんどなかった。
- 平均のズレは数拍程度だが、個人差は±20拍前後と非常に大きい。
- Arena・Tanaka・Gellish式が最も誤差が小さく、
Fox式は誤差は少し大きいが「全体的に安定している」式だった。
考察:年齢が依然として最大心拍数を決定する
この結果は、「心肺体力が高い人ほど最大心拍数が低くなる」とする一部の通説を明確に否定するものです。著者らは、「CRFはMHR誤差にわずかな影響しか持たず、年齢が主決定因子である」と結論づけています。
MHRは自律神経系、とりわけβ₁受容体感受性の低下や洞房結節の刺激伝導特性に依存しており、加齢によるβ受容体脱感作と洞結節のペースメーカ細胞の電気的リモデリングが、MHR低下の主要因とされています。これらの生理的変化は、運動による一時的な心機能強化よりも、加齢の累積的影響の方が強く作用します。したがって、VO₂max(代謝系の最大酸素利用能)が高いことは、必ずしも心拍上限の維持を意味しないのです。
また、Bland–Altman解析で得られた±20 bpmの誤差は、トレーニングゾーンを1〜2段階誤る可能性を示します。例えば「70%MHRでトレーニング」と設定した場合でも、実際には60%〜80%MHRの範囲で行っている可能性があるということです。
そのため、個人レベルではMHRを直接測定するか、RPE(自覚的運動強度)や速度・出力などの補助指標を組み合わせる必要があります。
新規性:CRFを変数として組み込んだ初の大規模探索
これまでのMHR研究は、年齢と性別のみに焦点を当てており、心肺体力という生理的変数を統計的に検証した研究は限られていました。本研究は、230名の実測VO₂maxデータを基に、CRFを連続変数として組み込み、その交互作用をLMMで解析した点で画期的です。
結果として、CRFがMHR推定誤差を大きく変えることはなく、「年齢ベースモデルの限界を確認しつつも、個別調整が不要な実務的妥当性」を再確認しました。つまり、現行の年齢ベース式は依然として「大まかに使う分には有用」という結論です。
臨床・実践的意義:予測式の使い方を見直す
本研究が示す実践的メッセージは明快です。
- 年齢式によるMHR推定は集団レベルでは妥当だが、個人では誤差が±10 bpm以上生じる。
- 心拍ゾーンを「175 bpm」と単一値で設定するのではなく、「170〜180 bpm」と幅をもって管理すべき。
- β遮断薬内服や高齢者など、心拍反応が鈍い症例ではRPE(13〜17)やパワー・速度など代替指標を用いる。
- トレーニングや臨床運動療法では、年齢式+RPE+HRモニターの併用が安全で現実的。
これにより、過負荷による心血管イベントを防ぎつつ、適正な運動処方が可能になります。
限界点と今後の展望
著者らは、以下の限界を明確に述べています。
- 対象が健康成人(主に男性)中心であり、高齢者や心疾患患者への一般化は限定的。
- 後方解析であり、サンプルサイズ設計が事前に行われていない。
- トレッドミル負荷試験の特性上、一部は「筋疲労」で終了し真のMHRに達していない可能性。
- β遮断薬や自律神経障害など、心拍反応を変化させる要因を除外できていない。
今後は、疾患群やエリートアスリートを含む個別生理モデルの開発が求められます。著者らは、将来的に機械学習を用いた個人化MHR推定モデルの構築を提案しており、これが精密運動医療への橋渡しになるとしています。
結論
本研究は、最大心拍数の年齢ベース推定式が「個人差の大きい現象」であることを改めて裏付けつつ、心肺体力という生理的要因がその誤差に大きく寄与しないことを示しました。
すなわち、「年齢こそがMHRの支配的因子であり、CRF補正による精度向上は限定的」という結論です。
臨床やトレーニング現場では、年齢式を目安としながらも、主観的運動強度や安全域を併用した柔軟な指導が求められます。
参考文献
Martin J, Lindsey B, Gerrity C, Ambegaonkar J. Exploratory analysis of the accuracy of age-based maximal heart rate equations across cardiorespiratory fitness levels. PLOS ONE. 2025;20(10):e0335842. doi:10.1371/journal.pone.0335842