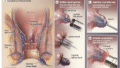2025 AHA/ACC Multisociety高血圧ガイドラインの記載を踏まえ、しばしば臨床上問題となる拡張期高血圧(Isolated Diastolic Hypertension, IDH)の病態と治療上の注意点を整理します。
Isolated Diastolic Hypertension(IDH)の概念
- 定義:収縮期血圧(SBP)が正常(<130 mmHg)で、拡張期血圧(DBP)が上昇(≥80 mmHg)の状態。
- 分類:
- DBP 80–89 mmHg → Stage 1 高血圧
- DBP ≥90 mmHg → Stage 2 高血圧
- ガイドラインは「SBPとDBPが異なるカテゴリーにある場合は高い方に分類する」と明記しており、IDHも他の高血圧と同様に扱うとしています。
病態と臨床的特徴
- 疫学的背景:若年者に多くみられます。動脈硬化がまだ進行していない段階で、末梢血管抵抗の上昇が主体です。
- 臨床的リスク:観察研究では心血管疾患リスク増加と関連。ただし収縮期高血圧に比べてエビデンスは弱い。
- 自然経過:中年以降にSBPも上昇して「収縮期+拡張期高血圧」へ移行する例が多いと報告されています。
IDH治療におけるリスクと慎重さ
- IDH(拡張期血圧のみ高い例)に薬物治療を行うと、収縮期血圧が正常なのにさらに低下、下がり過ぎる可能性があります。
- 特に若年者で、SBPがもともと110〜120 mmHg程度の症例では、過剰な降圧によりめまい、倦怠感、臓器灌流不足などが生じる懸念があります。
- 冠動脈血流は拡張期に依存するため、DBPが70 mmHg未満に下がると心筋虚血リスクが理論的に高まります。
- エビデンスの限界:IDH単独を対象とした大規模RCTは乏しく、推奨は主に観察データと総合的解釈に基づいています。
臨床での安全運用ポイント5か条
- まず生活習慣介入
- 低リスクのStage 1 IDHでは、直ちに薬物治療せず、3〜6か月の生活習慣改善(減塩・体重減量・運動)を優先する。
- 薬物は低用量から開始
- 薬物療法が必要な場合は、少量から開始し、収縮期の過降圧がないかを確認しながら調整する。
- 収縮期血圧の監視
- 治療中はDBPだけでなくSBPの変化を常にモニターし、SBPが100 mmHg台前半に下がるようなら投与量を見直す。
- 冠動脈疾患リスクを考慮
- 既往のある患者では、DBPを70 mmHg未満にしすぎないよう配慮する。めまい・胸痛などの症状を重視する。
- 若年者では将来を見据えた管理
- IDHは収縮期高血圧の前段階となり得るため、長期的な心血管リスク軽減を目的とした生活習慣指導を徹底する。
ガイドラインの立場をまとめると
2025 AHA/ACCガイドラインでは、IDHを特別に区別せず、収縮期・拡張期のどちらか高い方で分類し治療するとしています。原則は収縮期高血圧と同じ枠組みで治療対象ということです。
ただし、本文では「エビデンスはSBP主体であり、IDHに関するデータは限られる」ことを明記しており、強いRCTの裏付けはないとしています。
したがって、薬物導入時は症状や収縮期の過降圧に注意することが臨床的に求められると解釈されます。過降圧のリスクを常に念頭に置き、低用量から慎重に、症状を伴う変化を見逃さないことが実践的ポイントです。
参考文献
・Jones DW, Ferdinand KC, Taler SJ, et al. 2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGIM Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. J Am Coll Cardiol. 2025; doi:10.1016/j.jacc.2025.05.007