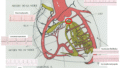はじめに
「少量の飲酒は健康に良い」という考え方は、長い間、人々の生活文化の中に根付いてきました。特に血圧については、3杯以上の飲酒が高血圧リスクを高めることは知られていましたが、1杯程度の飲酒がどの程度血圧に影響するのか、その答えは十分に明らかではありませんでした。また、多くの研究は横断研究であり、「飲酒を始めた」「飲酒をやめた」といった行動の変化が血圧にどう影響するかを深く検討した研究は非常に限られていました。
本研究は、日本の大規模健診データベースを用いて、飲酒行動の変化そのものが血圧変化にどのように結びつくかを、男女別、飲酒量別に詳細に検討した縦断研究です。対象者は58,943人、解析ユニットは359,717件という大規模データに基づき、飲酒の「開始」と「中止」が血圧値をどの程度動かすのかを統計学的に精緻に評価しました。
研究の結果は明確でした。
「飲酒をやめれば血圧は下がり、始めれば血圧は上がる」
しかも、その変化は“わずかな量”でも起こり、“量依存的”でした。
研究対象と方法:連続受診データを用いた縦断解析
対象となったのは、2012〜2024年に聖路加国際病院で健診を受けた人々です。20歳以上(年齢中央値50.5歳)で、少なくとも2回以上の連続健診データがあることが条件とされました。降圧薬使用者や透析患者は除外されています。
本研究の特徴は、解析を「連続した2回の健診を1ユニットとし、その間に飲酒が変化したかどうか」に基づいて行った点です。
明確に異なる二つのコホートで実施されました。
- 禁酒コホート(習慣的飲酒者が摂取を中止または減量した場合)
- インデックス受診時に習慣的飲酒者(週に1回以上飲酒)だった25,621人のデータ(53,156回の受診ペア)。
- 開始コホート(非飲酒者が摂取を開始または増量した場合)
- インデックス受診時に非飲酒者だった31,532人のデータ(128,552回の受診ペア)。
解析は2方向で実施されました。
- 飲酒を中止した人 vs 飲酒を継続した人
- 飲酒を開始した人 vs 非飲酒を継続した人
飲酒量は「1杯=エタノール10g」と定義され、酒種は問わず換算しています。主要アウトカムは収縮期血圧(SBP)、拡張期血圧(DBP)の変化量です。
交絡因子として、年齢、喫煙、運動、食事、BMI、トリグリセリド、HDLなどが調整され、さらにPropensityスコア解析による感度分析も行われています。
追跡期間の中央値は1.0年です。
結果:飲酒中止は血圧を下げ、開始は上げる
本研究で最も重要な結果は、「飲酒の変化は血圧を動かす」という確かなデータが得られたことです。
飲酒中止の血圧への影響
飲酒をやめた群では、1杯分の飲酒を中止するごとに
・SBP −0.92 mmHg
・DBP −0.82 mmHg
の低下が認められました。
量が多いほど効果は大きく、特に4杯以上飲んでいた人が禁酒すると
・SBP −5.61 mmHg
という、薬剤に匹敵する変化が出現しています。
男女差をみると、男性の方が低下幅はやや大きいものの、女性でも有意差をもって血圧低下がみられました。
飲酒開始の血圧への影響
逆に、今まで飲んでいなかった人が飲酒を開始した場合、1杯あたり
・SBP +0.78 mmHg
・DBP +0.53 mmHg
の上昇を認めました。
これも量依存性を示し、2〜3杯の開始では+2.73 mmHg、4杯以上では+4.35 mmHgの血圧上昇が見られました。
注目すべきは、女性でも0.5〜1杯/日という“ほぼ象徴的な飲酒量”ですら血圧上昇が検出された点です。
「女性の1杯は安全」という従来の価値観を根底から揺さぶる結果といえます。
酒種の影響:ビールでもワインでも日本酒でも同じ
「ワインは健康に良い」「焼酎は太らないから大丈夫」など、飲酒文化の中には多くの俗説があります。しかし本研究では、酒種別に解析しても血圧への影響方向はすべて同じでした。
つまり、
血圧を上げているのは「酒の種類」ではなく「エタノールそのもの」
ということです。
本研究の新規性
過去にも飲酒と血圧の関連を検討した研究はありましたが、多くは横断研究であり、飲酒行動の変化そのものを追跡できていませんでした。
本研究の新規性は以下の通りです。
- 飲酒量の増減を縦断的に追跡した世界最大級の研究であること
- 「軽度飲酒」ですら血圧に影響することを示した最初のエビデンスであること
- 女性においてもわずかな飲酒で血圧変化が検出されたこと
- 酒種別解析により“エタノール”が本体であることを示したこと
特に「1杯以下での上昇が確認された」という結果は、ガイドラインの定義に挑戦する重要な所見です。
生活者・臨床医が明日から活かせるポイント
・「1日1杯だけだから大丈夫」は根拠がありません
・禁酒は減酒よりも血圧改善効果が強いです
・高血圧患者では飲酒変化による血圧上下がさらに大きいです
・飲酒量を問診する際は「現状」よりも「変化」に注目する必要があります
・酒種を変えても血圧への影響は変わりません
・患者教育では「飲酒は血圧の可逆的要因である」と強調できます
・禁酒の効果は1年以内に明確に現れます
Limitation
・観察研究であり因果関係の証明はできません
・飲酒量は自己申告であり過小評価の可能性があります
・年間健診データのため短期間の血圧変動を捉えていません
・日本人データのため他民族への外挿は慎重に行う必要があります
・禁酒の理由(病気、行動変容、妊娠など)を統制できていません
結論
本研究は、軽度飲酒であっても血圧を上昇させ、飲酒中止は量依存的に血圧を低下させることを示した極めて重要な縦断研究です。わずか1杯未満の飲酒でも血圧は上昇し、その影響は女性でも明確に検出されました。
飲酒量の減少は、薬剤と同等の血圧改善をもたらす可能性があります。
高血圧診療の現場では「減塩」と同様に「減酒・禁酒」が科学的に正当化されるべき生活指導項目であることを、本研究は示しています。
参考文献
Minami Y, et al. Blood Pressure After Changes in Light-to-Moderate Alcohol Consumption in Women and Men: Longitudinal Japanese Annual Checkup Analysis. J Am Coll Cardiol. 2025; (in press).