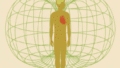序論
トマトは、医療・栄養学の世界で長らく「抗酸化食品の代表」として扱われてきました。リコピン、β‐カロテン、ビタミン類、食物繊維など、多様な生理活性成分を含み、抗炎症作用、抗酸化作用、抗動脈硬化作用の報告は枚挙にいとまがありません。しかし、これらの保護的作用が「いつ食べるか」、つまり季節によって変わりうるという視点は、これまで十分に検討されてきませんでした。
本論文(Lin et al., 2025)は、この「季節性」という新規の視点から、トマト摂取と死亡率の関係に切り込みました。対象は NHANES の 6,260 名、追跡期間は 10 年。この大規模データを用い、旬の時期(in-season)と非旬の時期(off-season)それぞれの摂取が、全死亡および心血管・脳血管死亡(CVD)にどう影響するのかを検証しています。
研究デザインと対象
解析対象6,260名(平均44歳(29-62))のうち、追跡10年間で604名(9.6%)が死亡しました。食習慣はFFQによって調査され、トマトは五段階の摂取頻度に分類されました。
Never(食べない)
No more than once per month(1か月に1回以下)
Once per month to once per week(月1回~週1回)
Once a week to once a day(週1回~1日1回)
One or more times per day(1日に1回以上)
Unknown(不明)
解析には、年齢、性別、人種、教育、所得比、喫煙、糖尿病、高血圧、脂質異常症などが調整されています。
本研究では「6〜8月を中心とした(地域差あり)、自然成熟の露地トマト」が旬のトマトとして扱われています。また、新鮮トマトとは「加工されていない、生のまま摂取されるトマト全般(サラダ・生食としてのトマト)」としています。
新鮮トマト摂取が全死亡を減らすという明確なシグナル
まず特筆すべきは、新鮮トマト全体の摂取と全死亡の明確な関連です。
・新鮮トマト摂取者は全死亡が約37%低下
HR = 0.63(95%CI 0.45–0.87, P = 0.005)
これは既存研究で示されてきた「トマト摂取と死亡率低下」という知見を支持しつつ、本研究ではより詳細に季節性を分解している点が新規性に当たります。
旬のトマトがもたらすのは「全死亡の低下」
興味深いことに「旬の時期のトマト」は、摂取全体では有意な関連はありませんでした。しかし頻度ごとに詳細に見ると、ある一点で明確なシグナルが現れます。
・週1回〜1日1回の旬トマト摂取で全死亡が52%低下
HR = 0.48(95%CI 0.24–0.95, P = 0.034)
旬の時期は供給量が多く、日常的に生鮮野菜を摂取しやすい季節でもあります。また、夏季はCVDイベントが減少する季節であるため、CVD死亡よりむしろ「全死亡」への影響として現れた可能性があります。
非旬トマトの摂取が示した予想外の結果
もっとも本研究で最も新規性が高い部分は「非旬のトマト(off-season)」の結果です。
・非旬トマトは全死亡には影響しない
・しかしCVD死亡を一貫して低下させる
SHR = 0.43(95%CI 0.23–0.79, P = 0.006)
さらに頻度ごとの解析では、
月1回以下〜1日1回以上のすべてのカテゴリーでCVD死亡が有意に減少しました。
これは従来の「旬の食材のほうが栄養価が高い」という一般的認識とは異なり、非常に興味深い結果です。
なぜ非旬トマトでCVD死亡が下がるのか
本論文では、以下のメカニズムが示唆されています。
- 温室栽培の管理条件が栄養成分を高める可能性
温室では光量・温度管理が可能で、リコピンやビタミンCなど抗酸化成分が増加する報告があります。 - 冬季のCVDリスク増大を補う可能性
冬は交感神経刺激、血圧上昇、脱水、食塩過多、脂質異常などが重なりCVDイベントが増加します。
その季節に抗酸化食材であるトマトを摂取することがリスクを打ち消した可能性があります。
季節性と温室栽培という2つの要素が重なる点が、新規性として際立ちます。
加工品:ケチャップは有益だがジュースは注意が必要
ケチャップ(catsup)
加熱加工によりリコピンがcis型へ変換され、生体吸収が高まるとされます。本研究ではその利益が明確に示されました。
・週1回〜1日1回で全死亡低下(HR = 0.62)
・同頻度でCVD死亡低下(SHR = 0.53)
過剰摂取ではなく「中等量の摂取」が鍵です。1日1回以上の摂取で死亡リスクが上昇する傾向があります。
トマトジュース
こちらは異なる結果となりました。
・1日1回以上で全死亡増加
HR = 1.49(P = 0.042)
ナトリウムや糖分など添加成分の影響が推測され、摂りすぎはむしろ健康に不利となる可能性があります。また、他にもバイアスの存在が疑われます(→補足参照)
リコピン濃度と死亡リスクの関係
血中リコピン濃度は、全死亡・CVD死亡の双方で明確に逆相関を示しました。
・total lycopene:HR = 0.99
・trans-lycopene:HR = 0.98
リコピンはミトコンドリア膜や細胞膜に高濃度で存在し、脂溶性抗酸化物質として、LDL酸化、内皮障害、慢性炎症を抑制すると考えられます。分子レベルでの説明が明記されていないものの、抗酸化作用を通じてCVDリスク低減に寄与する可能性が強く示唆されます。
臨床的・実践的な示唆
明日から活かせる点として次の3つが重要です。
- 週1回以上、旬のトマトを日常的に摂ることは全死亡を減らす可能性がある
- 冬季(非旬)には、温室トマトを適度に取り入れることでCVDリスクの低減が期待できる
- トマトジュースの過剰摂取は控え、ケチャップは中等量にとどめる
特にCVDハイリスク患者への栄養指導では、季節性を意識した具体的な食事提案が実践しやすい利点があります。
限界点
論文は以下の限界を明記しています。
- NHANESは米国人口であり、他地域に一般化できない。
- FFQはベースライン1回で、10年間の食習慣変化を反映できない。
- 摂取量が頻度分類にとどまり、正確な量的把握が難しい。
- 観察研究で因果関係は証明できない。
- リコールバイアスや残余交絡因子の可能性が残る。
結論
この研究の最大の新規性は、トマト摂取の効果が単に「摂取量」や「頻度」ではなく、「季節」という要因によって大きく変化することを示した点にあります。旬のトマトは全死亡の低下に、非旬のトマトは心血管・脳血管死亡の低下に寄与し、それぞれ異なる健康効果を示しました。
トマトという身近な食材が、季節性や栽培環境によって異なる生体効果をもたらすという事実は、今後の栄養疫学に新たな視点を提供するものです。
参考文献
Lin J, Li J, Wang L, Cui M, Chen L. Seasonal variations in the connection between tomato consumption and all-cause and cardio-cerebrovascular mortality. Food & Nutrition Research. 2025;69:12302. doi:10.29219/fnr.v69.12302.
参考
補足:トマトジュースは本当に死亡リスクを上げるのか?
「トマトジュースを1日1回以上飲むと全死亡が上昇(HR 1.49)」 という結果は、下記記事のRCTなどの結果とは明らかに異なります。
では、なぜ逆の結論が出るのか?
以下に、医学研究の構造とデータの性質から、最も妥当な理由の推測を整理します。
1. まず前提:今回の論文は「観察研究」である
今回の研究は
トマトジュース摂取と死亡率の“関連”を推測する疫学研究
です。
一方、これまでの「トマトジュースは血管に良い」という話は、
RCTや短期介入での“因果”に近い証拠でした。
“関連”と“因果”、この違いは非常に大きいです。
2. 観察研究でトマトジュース=全死亡増のように見える理由(推測)
推測①:トマトジュースを飲む人の背景リスクが高い(逆因果性)
観察研究では「その食品を飲む人の背景が影響する」ことがよくあります。
例えば…
- 高血圧や動脈硬化があり健康に不安 → 生活改善のためトマトジュースを飲み始める
- すでに肥満・脂質異常・糖尿病がある → 健康食品としてトマトジュースを選びやすい
- 食事の質が低く、代替的にジュースで栄養を補おうとする
すると 既にリスクが高い層が「トマトジュース群」に偏りやすい ため、
統計モデルで調整しても、真の因果を完全には除去できません。
→ 典型的な観察研究の「残余交絡」。
推測②:飲み方の問題(果汁ジュース的飲み方を含む可能性)
研究で用いられた“トマトジュース”の定義が、市販の以下のような多様な製品を含んでいた場合
- 加塩トマトジュース
- 他の果物の混合製品
- 砂糖を添加した製品
- その他の添加物含有製品
これらは 無塩・無加糖の100%トマトジュースとは健康影響が異なる ため、
「トマトジュース=有害」という誤解が生じやすくなります。
特に加塩タイプは塩分摂取を増やし、死亡リスクと関連しても不思議ではありません
推測③:内皮機能改善=死亡率低下 ではない(中間指標の限界)
FMD改善は「動脈の反応性が良くなる」という生理学的効果であり、
すぐに死亡率に反映されるものではありません。
RCTは短期間(8〜12週間)
死亡率研究は長期間(数年〜十数年)
時間スケールが全く違うため、結果が一致しないのは当然とも言えます。
では、どちらを信じるべきか?
以下のように整理するのが最も学術的に正確です。
● RCT
因果に強く、短期的な生理学効果(FMD改善)が明確。
● 観察研究
因果ではなく“関連”であり、残余交絡の影響が大きい。
今回の「全死亡が増える」というデータは、
交絡の可能性が高く、直接的な因果を示すものではない
と解釈するのが医学的に妥当です。
補足の結論
- トマトジュースの心血管改善効果は RCTで示されている
- 一方で、「1日1回のトマトジュース摂取で全死亡が上昇」という観察研究は
交絡の可能性が高い“弱い関連”であり、因果関係ではない
→ 医学的には“害がある”とは判断できず、むしろ無塩100%トマトジュースは健康食品として妥当