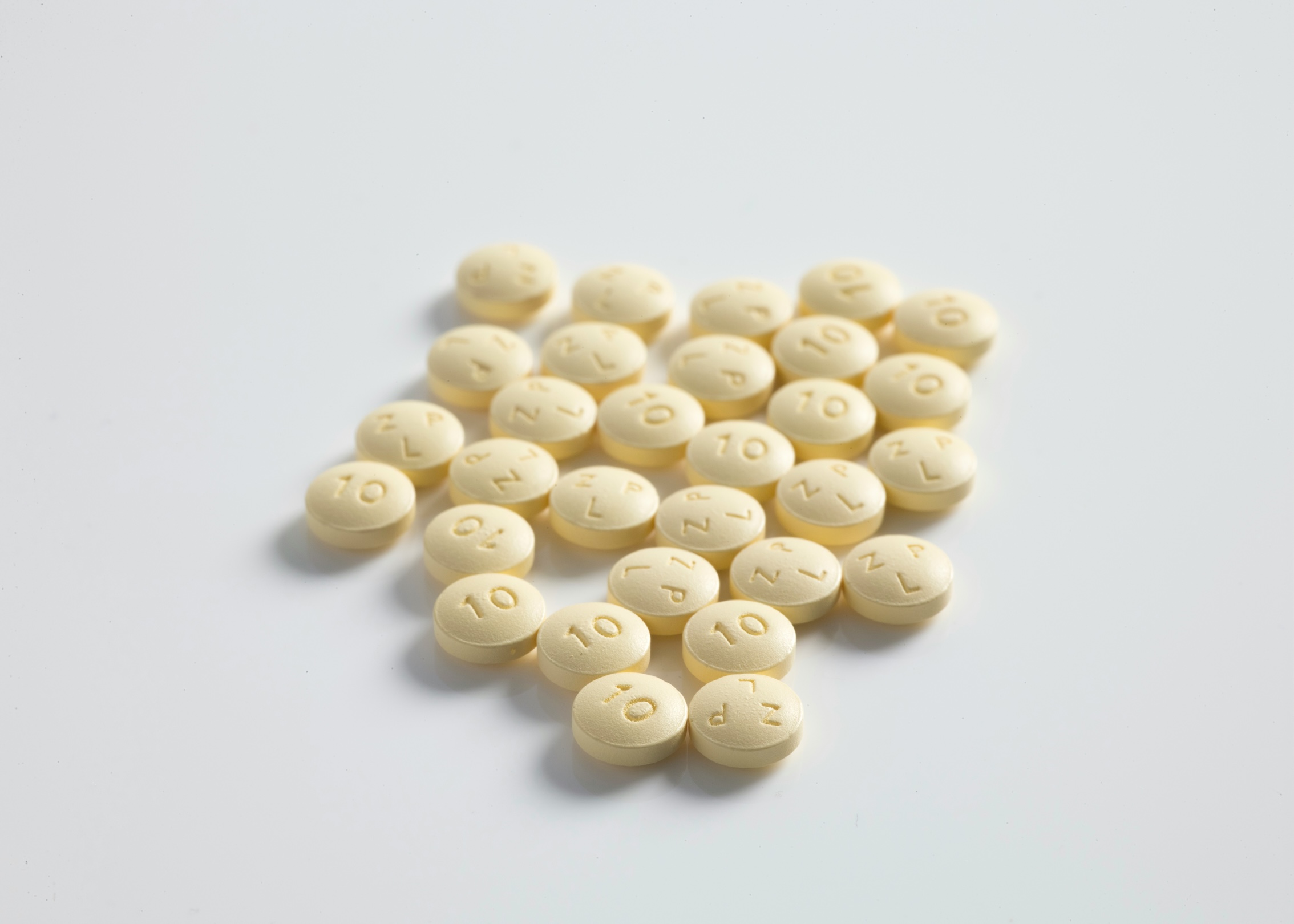はじめに:糖尿病薬が心血管治療の主役に躍り出る
近年、SGLT2阻害薬(SGLT2i)は、単なる血糖降下薬という枠を超えて、心血管保護薬としての地位を確立しつつあります。もともとは2型糖尿病(T2DM)の治療薬として開発されたこの薬剤群が、心不全、慢性腎臓病、そして動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)にも効果を示すという事実は、臨床医にとってパラダイムシフトとも言えます。本稿では、Ceasovschihらの最新レビューをもとに、SGLT2iの抗動脈硬化作用について、分子機序から臨床試験データまでを解説いたします。
分子レベルで読み解くSGLT2阻害薬の抗動脈硬化作用
SGLT2は近位尿細管S1・S2セグメントに局在し、1日に約1モルのグルコースを再吸収しています。SGLT2阻害薬はこの機能を阻害することで、血糖を低下させますが、注目すべきはその「プレオトロピック効果(多面的な効果)」です。
抗炎症作用と免疫調整
動物実験では、エンパグリフロジン、ダパグリフロジン、イプラグリフロジンが、TNF-α、IL-6、MCP-1といった炎症性サイトカインの産生を抑制し、マクロファージの泡沫化や血管内皮への接着・浸潤を抑えることが示されています。また、NLRP3インフラマソームの活性を阻害することで、動脈硬化の進行を抑制する可能性も示唆されています。
オートファジーの正常化
オートファジーは細胞内恒常性を維持する重要なプロセスであり、SGLT2iはAMPK–mTOR経路やSIRT3、GSK3βなどを介してオートファジーを促進します。過剰なオートファジーがプラーク破綻を引き起こす場合には、その調整作用も働くと考えられています。
細胞老化と線維化の抑制
カナグリフロジンはAMPKの活性化を通じて老化関連分子PD-L1の発現を抑制し、免疫細胞による老化細胞の除去を促進します。これは心筋線維化の抑制や心不全の進行防止に貢献します。
プラーク安定化と血管リモデリング
SGLT2iは血管内皮細胞の老化遺伝子の発現を抑制し、NO合成を促進して血管拡張を導きます。ダパグリフロジンは動脈硬化プラークの大きさと負荷を減少させ、エンパグリフロジンは血管平滑筋細胞(VSMC)のDNA合成を抑制して内膜肥厚を防ぎます。
代謝全体への作用
SGLT2iは血糖をインスリン非依存的に低下させるほか、脂質プロファイル改善、体重減少、尿酸排泄促進、ケトン体産生促進、赤血球産生増加(ヘプシジン抑制による)など、幅広い心血管リスク低減作用を持ちます。
前臨床から臨床へ:エビデンスの積み重ね
脂質代謝への影響
動物実験では、エンパグリフロジンやダパグリフロジンが肝臓での脂肪合成を抑制し、脂肪酸のβ酸化を促進することが示されました。ヒトでは一貫した結果ではないものの、非空腹時測定ではトリグリセリド低下や糞中コレステロール排泄増加が観察されています。
動脈スティフネスの改善
PWVやAIxの改善がいくつかの臨床研究で確認されています。たとえば、T2DM患者40名の前向き研究では、PWVが10.68→9.96 m/sへと有意に改善しました。ただし、複数のメタ解析では有意差が得られず、糖尿病の有無や併存疾患が影響する可能性があります。
冠動脈疾患における有効性
EMPA-REG試験では、エンパグリフロジンが心血管死を36%、全死亡を32%低下させました。DAPA-MI試験では、ダパグリフロジンが心筋梗塞後10日以内の患者で34%の総合的臨床ベネフィットを示しました。ただし、心血管死の有意な減少は得られておらず、さらなる研究が必要です。
末梢動脈疾患と切断リスク
カナグリフロジンはCANVAS試験で下肢切断リスクの上昇(特に足趾レベル)を示しましたが、エンパグリフロジンやダパグリフロジンではPAD患者における有害事象の増加は認められていません。EMPEROR試験のメタ解析によると、末梢動脈疾患(PAD)を有する患者では、SGLT2阻害薬による心血管イベントの予防効果が特に顕著であり、イベント発生率の絶対的な低下量(絶対リスク減少)は非PAD患者よりも大きくなっていました。一方で、治療によるリスクの割合的な減少(相対リスク低下)は、PADの有無にかかわらずほぼ同じでした。
脳血管疾患と認知症
SGLT2iは虚血性脳卒中には中立的とされますが、出血性脳卒中に対しては50%のリスク低下をもたらしたという報告があります。また、CKDや心房細動を有するT2DM患者においては脳卒中リスクの20%低下が示唆されており、認知症発症率も低下する可能性があります。
他薬剤との併用と安全性
スタチンとの併用に関しては、BCRP(乳がん耐性タンパク)阻害を介してスタチン血中濃度上昇・筋毒性の可能性が示されていますが、臨床的な意義は小さいと考えられています。アスピリンやRA系薬剤との有意な相互作用は報告されていません。
副作用としては、女性で10%、男性で3%の尿路真菌感染、稀ながら糖尿病性ケトアシドーシス(DKA、入院患者で0.2%)、低血圧、急性腎障害、フォルニエ壊疽、骨折や切断などが報告されています。とくに高リスク患者においては注意が必要です。
明日から臨床に活かすために
SGLT2iは、心不全やCKDだけでなく、動脈硬化性疾患における「リスク修飾薬」としての役割が期待されています。冠動脈疾患やPADの既往があるT2DM患者では、SGLT2iの導入がMACEの抑制に直結する可能性があります。特に心筋梗塞後の早期介入や、切断リスクの高いPAD患者において、薬剤選択の際には個別の安全性プロファイルを考慮する必要があります。
おわりに
SGLT2阻害薬は、その多彩な作用機序を通じて動脈硬化性疾患に新たな治療の選択肢を提供しつつあります。臨床試験では主に二次予防における効果が示されており、一次予防への応用には今後の研究が待たれます。特定の薬剤における安全性プロファイルの違いや、併用薬との相互作用も踏まえた上で、患者ごとに最適な治療戦略を立てていくことが求められます。
参考文献
Ceasovschih A, Balta A, Shams Aldeen E, et al. Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors and Atherosclerosis. Am J Prev Cardiol. 2025;101061. https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2025.101061