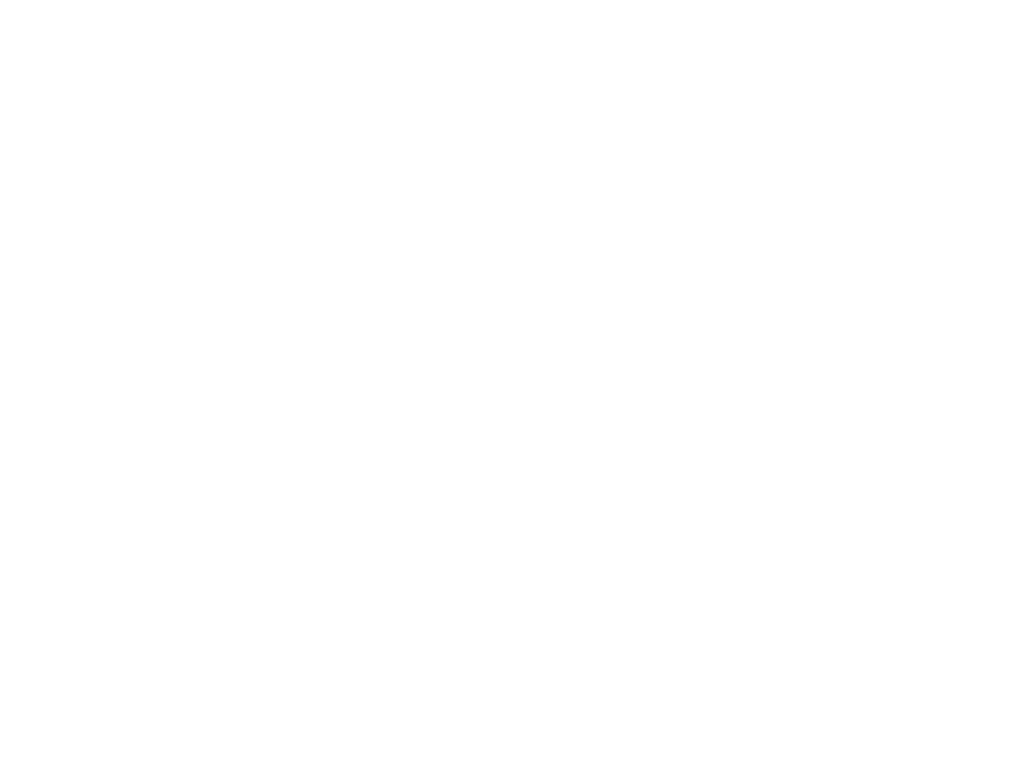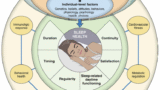はじめに
加齢とともに認知機能が低下するのは自然な現象とされていますが、生活習慣のなかでも「睡眠」は、その進行に影響を与える最も重要な要因の一つです。近年では睡眠と認知機能の関連がさまざまな研究で示唆されていますが、その多くは単一の睡眠指標(例:睡眠時間)と単一の認知ドメイン(例:記憶)との一変量的な関係に注目したものでした。しかし、睡眠も認知機能も本来は多次元的な構造をもつ複雑な生理機能です。本研究では、多変量解析手法である部分最小二乗相関(Partial Least Squares Correlation:PLSC)を用いることで、この複雑な関係性をに迫っています。
対象は773人のシンガポール在住高齢者(65-80歳)であり、睡眠は最大28日間のOura Ringによる客観的評価、認知機能は7つのドメインにまたがる10の標準化テストで評価されました。多面的な睡眠指標(23項目)と多様な認知機能領域(7領域)を多変量解析(PLSC)を用いて包括的に評価した点に大きな新規性があります。
Oura Ringはシンガポール人集団で検証済みで、信頼性の高いデータが得られています
こちらも参考に。
睡眠と認知の関係を捉える新たな視点:多変量解析の意義
睡眠評価では、Oura Ringを用いて23の睡眠指標を4つのカテゴリー(タイミング、持続時間、継続性、規則性)に分類して測定しました。
認知機能評価では、7つの認知領域(言語記憶、視覚記憶、実行機能、注意力、視空間能力、処理速度、言語)を10の標準化されたテストで包括的に評価しました。テスト得点はTスコアに変換され、複数のテストで評価された領域は平均値が使用されました。
従来の一変量解析では、睡眠時間が長すぎても短すぎても認知機能が低下するというU字型の関係が報告されてきましたが、本研究では睡眠の「長さ」ではなく、「継続性」と「規則性」が認知機能との関連性を持つ主要な因子であることが明らかになりました。
PLSC解析により、23の睡眠指標と7つの認知ドメイン間の共分散構造のうち82%が第1主成分により説明され、睡眠スコアと認知スコアの相関係数は0.2(p < 0.001)と統計的に有意でした。この相関の大きさは、脳容積や心血管リスクスコアと認知機能の関連で報告されている値(r=0.15〜0.25)と同程度であり、十分に臨床的意義があると考えられます。
睡眠の「規則性」と「継続性」が鍵
ブートストラップ法によって抽出された11の有意な睡眠指標のうち、3つは睡眠の継続性(WASO、睡眠分断指数SFI、睡眠効率のばらつき)、8つは睡眠の規則性(睡眠規則性指数SRIや各種指標のiSD)に分類されました。一方で、平均睡眠時間や就寝・起床時刻といったタイミング指標は、認知機能との相関が認められませんでした。
特に注目すべきはSRI(Sleep Regularity Index)です。この指標は、「同じ時間帯に眠っているか否か」という点を日ごとに比較して算出され、100に近いほど規則正しい睡眠リズムを意味します。本研究では、SRIが記憶・実行機能・処理速度のすべてと有意に相関し、最大でr=0.17という関連が確認されました。これは、平均睡眠時間や睡眠効率といった他の指標よりもはるかに広範な認知ドメインと関連することを示しています。
また、睡眠の継続性指標は主に処理速度との関連が強く、夜間覚醒の多い「断片化された睡眠」が、脳の情報処理スピードに悪影響を及ぼす可能性が示唆されました。これは脳幹–皮質系の再統合や注意資源の配分に影響するためと考えられます。
- 睡眠規則性指標(特にSRI)は言語記憶、実行機能、処理速度の3領域すべてと相関
- 睡眠継続性指標(睡眠効率、睡眠断片化指数など)は主に処理速度と相関
SRIは実践可能なデジタルバイオマーカーになりうる
SRIの利点は、睡眠時間の単なる平均と異なり、日々のばらつきやライフスタイルのリズムまで反映できる点にあります。たとえば、同じ7時間の平均睡眠でも、日によってバラつきが大きければSRIは低下し、それが認知機能の低下と関係する可能性があります。SRIは連続的かつ非侵襲的に記録可能であり、Oura Ringなどの市販のウェアラブルデバイスでも取得が可能です。この点から、SRIは将来的に認知症リスク評価のデジタルバイオマーカーとして活用される可能性があります。
認知ドメインとの関連性
本研究で関連が認められた認知ドメインは、記憶(Rey Auditory Verbal Learning Test)、実行機能(Color Trail Test 2, Design Fluency Test)、および処理速度(Symbol Digit Modalities Test)でした。これらはすべて加齢により著しく低下する「流動性知能」の要素に含まれており、睡眠の質の低下がこれら機能の加齢性衰退を加速させる可能性があります。
本研究の限界と今後の課題
いくつかの制約もあります。まず、対象年齢が65〜80歳に限られ、60代前半や高齢者予備群が含まれていない点があり、結果の一般化には注意が必要です。また、閉塞性睡眠時無呼吸症(OSA)については自己申告による評価のみで、終夜睡眠ポリグラフなどの客観的診断がなされていないため、OSAによる交絡の可能性が否定できません。
さらに、横断研究であるため、睡眠の乱れが認知機能を低下させるのか、あるいは逆なのかという因果関係は明らかではありません。将来的には、SRIを用いた縦断研究や介入研究によって、睡眠改善が認知機能に与える因果的影響を明確にする必要があります。
実践的な応用とアドバイス
この研究結果から、高齢者の認知機能維持のために以下の実践が推奨されます:
- 認知機能の多面的評価:記憶力だけでなく、処理速度や実行機能にも注意を払い、これらの変化を早期に検出することが重要です。
- 睡眠の規則性を重視:就寝時刻と起床時刻を毎日一定に保つことが重要です。SRIを高めるためには、週末も含めて毎日同じスケジュールを維持する必要があります。
- 睡眠の連続性を改善:中途覚醒を減らすための対策(寝室環境の改善、カフェイン摂取の制限、適度な運動など)が処理速度の維持に役立つ可能性があります。
- ウェアラブルデバイスの活用:Oura Ringのようなデバイスで自分の睡眠パターンを客観的に把握し、特に規則性(SRI)に注目して改善を図ることができます。
おわりに
本研究は、加齢に伴う認知機能低下の予測因子として、従来見落とされがちだった「睡眠の規則性」と「継続性」に焦点を当てた点において、非常に重要な貢献をしています。とくに、SRIのような指標は、今後の高齢者ケアやパーソナライズド・ヘルスモニタリングの中核となる可能性を秘めています。数の認知領域(言語記憶、実行機能、処理速度)と関連していることが示されたことは、臨床的にも公衆衛生的にも重要な知見です。睡眠時間やタイミングに焦点を当てた従来のアプローチから、睡眠の連続性と規則性を重視した新しいパラダイムへの転換が求められるでしょう。
参考文献
Qin S, Ng EKK, Soon CS, Chua XY, Zhou JH, Koh WP, Chee MWL. Association between objectively measured, multidimensional sleep health and cognitive function in older adults: cross-sectional wearable tracker study. Sleep Medicine. 2025. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2025.106569