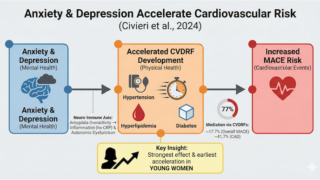 心療内科
心療内科 不安や抑うつで加速する心血管疾患
はじめに 心の平穏が失われたとき、私たちの身体の中では、目に見えない「時計」が加速を始めます。不安や抑うつといった精神的苦痛が、単なる感情の揺らぎにとどまらず、心血管疾患(CVD)という致命的な結末へと向かうプロセスを、代謝リスク因子の発生...
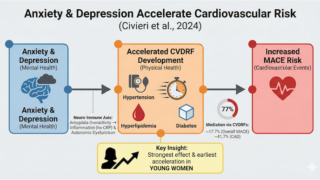 心療内科
心療内科  心臓血管
心臓血管 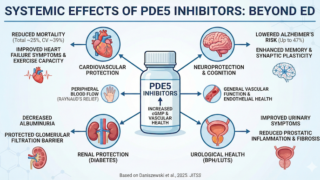 ED
ED 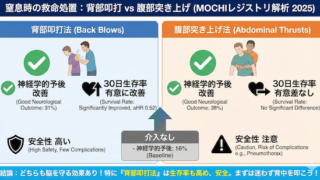 呼吸
呼吸 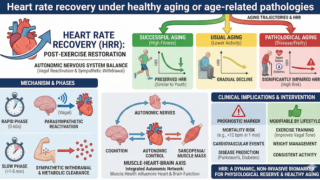 心拍/不整脈
心拍/不整脈 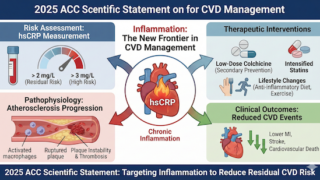 心臓血管
心臓血管 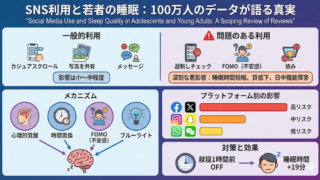 Digital Health
Digital Health 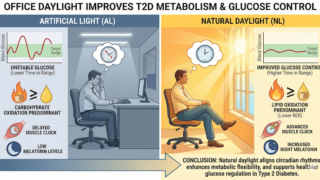 生活環境
生活環境 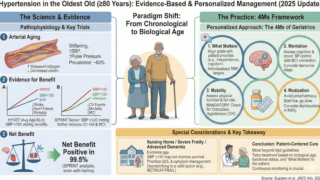 血圧
血圧 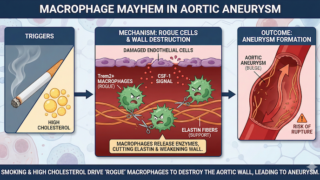 心臓血管
心臓血管