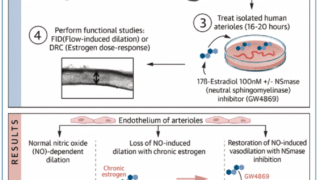 女性医療
女性医療 低用量ピル、ホルモン補充療法の副作用のメカニズムに迫る;エストロゲンの光と影
序論:エストロゲンの「二面性」をめぐる再考 長らくエストロゲンは「心血管保護ホルモン」として知られてきました。女性における閉経後の心血管リスク上昇は、エストロゲン欠乏が原因の一つとされ、ホルモン補充療法(HRT)はその予防策と考えられてきま...
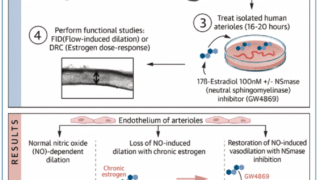 女性医療
女性医療  耳鼻咽喉科関連
耳鼻咽喉科関連  身体活動
身体活動  がん、悪性腫瘍
がん、悪性腫瘍  がん、悪性腫瘍
がん、悪性腫瘍 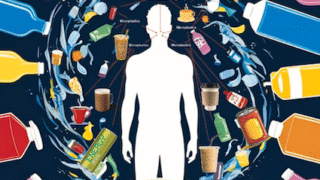 食事 栄養
食事 栄養 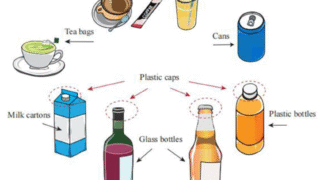 食事 栄養
食事 栄養  生活環境
生活環境  中枢神経・脳
中枢神経・脳  食事 栄養
食事 栄養